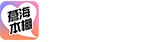アメリカ、九江市、東日インテリア会社の受付。
「こちらは方子昂様のご注文のコーヒーですが、どちらにお届けすればよろしいでしょうか?」
逢坂天馬は、紙袋を慎重に持ちながら、中のコーヒーをこぼさないように気を付けていた。
受付の女性アシスタントは逢坂天馬を頭からつま先まで見下し、嫌悪感を隠さずに言った。 「ついてきて。 」
逢坂天馬は本来、ウーバーの運転手だったが、今日は特別に追加料金のつくデリバリー注文を受け、急ぎの200ドルのためにここに来ていた。
しばらくして、逢坂天馬は女性アシスタントに従い、オフィスの扉の前に到着した。
逢坂天馬がオフィスのドアノブに手をかけた瞬間、中から突然、女性の情熱的なうめき声が聞こえてきた。
この声は、逢坂天馬にとってとても馴染み深く、自分の妻、神谷千尋の声に似ていた。
いや、きっと聞き間違いだ。
しかし、逢坂天馬はどうしても耳を澄ませずにはいられなかった。
「ああ…方総、やめてください…」
「ちょっとキスさせてくれよ。 どうせ君のあの無能な夫は一度もキスしてくれないんだろう?」
逢坂天馬はこの会話を聞いて、ショックで呆然とした。
そして、彼は急にドアを叩き、大声で叫んだ。 「開けろ!開けろ!」
受付のアシスタントは慌てて言った。 「何を騒いでいるの?」
ドン。
ドアが勢いよく開き、見知らぬ男が逢坂天馬の前に現れた。
注目を引くのは、彼の右頬に付いた口紅の跡だった。
逢坂天馬はコーヒーを投げ捨て、方子昂を押しのけて室内を見渡した。
そこには、白い肌で曲線美のある、黒いストッキングを履いた女性が、慌てて胸元のボタンを整えているところだった。
「神谷千尋!」逢坂天馬は怒りの声を上げた。
目の前のこの慌てた女性は、まさに彼の妻だった。
逢坂天馬は胸が締め付けられるように感じ、息ができなかった。
彼は怒りを込めて神谷千尋を見つめた。 「神谷千尋、俺たち結婚して三年だ。 昼間はウーバーの運転手をして、夜はお前たち一家の世話をしてきた。 苦労は言わないが、少なくとも誠実に尽くしてきたつもりだ!」
「この三年間、お前は一度も俺に触れさせてくれなかった! 俺はずっとお前が信念を持った女性だと思っていたのに、今日、お前はオフィスで他の男といちゃつくなんて!どうしてこんなことをするんだ!!」
「旦那!あなた…どうしてここにいるの!」
神谷千尋はようやくボタンを留め、露出していた胸元を隠した。
方子昂は悪意のある笑みを浮かべ、得意げに言った。 「毎日君が旦那を無能と罵るのを聞いていたから、どれほど無能か見せてもらおうと思ってね。 」
そう言って、方子昂は逢坂天馬を上から下まで軽蔑するように見下ろした。
最初は少し驚いていた神谷千尋も、状況を理解すると、いつもの態度に戻った。
彼女は心の中で思った。 逢坂天馬はただの婿入りで、車を借りるお金さえも自分が出している。 逢坂天馬に自分を非難する資格なんてない。
彼女は二人の間に立ち、頭を高く上げて言った。 「逢坂天馬、口を慎みなさい。 何がいちゃつくだって?私は方総とビジネスの話をしていただけよ!」
逢坂天馬は歯を食いしばり、冷笑して言った。 「ビジネスの話に触れ合いが必要で、口紅の跡だらけになるのか?」
受付のアシスタントはドアの前に立ち、全身を震わせる逢坂天馬を見て嘲笑した。 「自分を鏡で見てみなさい。 あなたはただのウーバー運転手に過ぎない。 方総の東日会社は時価総額が十億ドルもあるのよ! あなたが百年間ウーバーを運転しても、方総の足の指一本にも及ばないわ!」
方子昂はさらに傲慢になり、神谷千尋の肩を抱き寄せ、テーブルの上のワイングラスを手に取り、神谷千尋に差し出した。
神谷千尋は一瞬ためらったが、その後彼とグラスを合わせ、二人は一気に飲み干した。
逢坂天馬は目の前の共謀者たちを鋭く見つめ、拳を強く握りしめ、爪が肉に食い込んだ。 彼の心には怒りしかなかった。
アシスタントはそれを見て、眉を上げて言った。 「どうするつもり?手を出すのか? 警備員はどこにいるの?」
神谷千尋もまた頭を上げ、冷たく言った。 「逢坂天馬、まだ帰らないの?殴られたいの?」
逢坂天馬は警棒を持った警備員たちを一瞥し、ゆっくりと拳を解き、冷たい声で言った。
「神谷千尋、いつか後悔しないことを願うよ!」
そう言って、彼は会社の門をくぐり抜けた。
神谷千尋は眉をひそめ、逢坂天馬の去っていく背中を見つめながら、何も言わなかった。
……
車に乗り込み、逢坂天馬はどうやって二人に復讐するかを考えていた。
その時、逢坂天馬の携帯電話が突然鳴り出した。
電話の向こうから李執事の年老いた声が響いた。
「若旦那様、神谷家での三年間の婿入りとしての心性修行が、今日正式に終了しました。 報酬として雲頂山荘の別荘一軒が贈られます。 今日から、あなたの封印された能力が使用可能です。
」 「次の修行任務は商業修行で、旦那様が帝豪グループを買収し、あなたを社長に任命しました。
」 「分かりました。 」 逢坂天馬はしわがれた声で答え、特に大きな反応は示さなかった。
電話の向こうはさらに問いかけた。 「神谷夫人との関係はどうですか? 本当の結婚式を挙げ、彼女に正式な身分を与えるつもりですか?」
逢坂天馬の顔は冷たくなり、言った。 「必要ありません。 彼女にはその資格がない。 」
 GOOGLE PLAY
GOOGLE PLAY
/0/17068/coverbig.jpg?v=6e0cc2ef22d0e4fe899fa466e8cba6c6)

/0/16915/coverbig.jpg?v=89ed53f6c82d5aef26b777477a92c084)
/0/16871/coverbig.jpg?v=41d448583624096a3538ad44241991a3)
/0/17126/coverbig.jpg?v=c284a537dace42787d987069265d4245)
/0/1217/coverbig.jpg?v=def0503074338784a1a0a4beb2a81d34)
/0/16912/coverbig.jpg?v=6094500432b1f7394a537c696ae01d2f)
/0/17055/coverbig.jpg?v=572f2f1945fcfe3d6eefc25a610450e5)