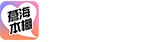夜が更けた。
大西結月は、眠りながらも不安で落ち着かない感覚に苛まれていた。
誰かに身体を押さえつけられ、息もできないほどだった。
耳元では、重く荒い呼吸が聞こえる。
続けて、下半身に鋭い痛みが走った。
何が起きているのかを察した瞬間、結月は恐怖で目を見開いた。ぼんやりと、自分の上に覆いかぶさる男の姿が見えた。
「たかなお……あなたなの?」
その男は喉の奥で軽く「うん」と声を漏らし、強い酒の匂いをまとっていた。それ以降は、言葉を発することなく、ひたすら彼女に激しく迫ってきた。
その声を聞いて結月は少し安心し、彼の動きに合わせるうちに、次第に身体も反応しはじめ、喉から甘く艶やかな声が漏れ出す。
攻めがさらに激しさを増し、結月は痛みを堪えながらも、曖昧な熱に身を委ね、まるで夢の中に浮かんでいるような感覚に包まれた。
結婚して3年。北川剛直が、ついに彼女に触れてくれたのだ!
彼女は、爺様が無理やり押しつけた妻だったため、剛直はこれまでまともに彼女を見ようともしなかった。
今回、どんな理由であれ、彼が彼女の部屋に入ってきたことが嬉しかった。
ただ、それだけで、胸がいっぱいだった。
2時間後、重く低い唸り声と共に、剛直は彼女の上に疲れ果てたように崩れ落ちた。 窓の外には月明かりが射し、彼の完璧な体のラインを柔らかく浮かび上がらせていた。
結月は、彼の激しく早い心音を耳で感じた。あまりに現実的でありながら、まるで夢のようだった。
これが夢なら、永遠に覚めたくない―そう願った。
彼の首筋に腕をまわし、運動のあとの荒い息を漏らしながら、結月は囁く。「たかなお…たかなお、わたし…ほんとうに…」
「大好き」――そう言おうとしたその瞬間、彼のかすれた声が耳に届いた。
「みやこ…」
結月はその場で石のように固まった。
心の奥がぎゅっと痛み、血の気が一気に引いていく。
「みやこ」――それは、呉宮京子の愛称。彼の初恋の人であり、剛直の心にいまだ残る「初恋」。明田様の事情により、彼女はずっと海外で暮らしていた。
しかし昨日、呉宮京子は帰国したばかりだった。
そして、結月に挑発的なメッセージを送ってきたのだ。
「結月、帰ってきたわ。北川家にあなたの居場所はない!」
「私はたかなおと幼なじみよ。あなたがこの数年で私の代わりになれると思ってるの?」 「出て行きなさい、孤児院に戻りなさい。そこがあなたの居場所よ。」
「あなた、たかなおがどれほど私を愛してるか知らないでしょ?彼があなたのベッドにいても、きっと私の名前を呼ぶわ。あなたは私の代用品にすぎないのよ、結月―その現実、辛いでしょ?」
代用品…?
彼女は明田様に認められた、正真正銘の北川家の嫁、大西結月。誰かの代わりなんかじゃない。
けれど耳元では、まだ剛直が「みやこ……みやこ……」と呟き続けていた。
あのひとつひとつのメッセージが脳内でこだまし、彼女がどれほど自分を偽っていたかを突きつけてくる。
突然、涙が止められないほど溢れてきて、結月は拳をぎゅっと握りしめ、全身が震えるほど悔しさを堪えた。
この数年、彼女はひたすら気を遣い、剛直のために仕事も辞めて、理想の妻であろうと努力してきた。
北川家の姑や小姑は、彼女の出自が不明なことや貧しさを嫌い、繰り返し嫌がらせをしてきたが、彼女は剛直に迷惑をかけたくなくて、すべて自分で飲み込んだ。
ただ、彼の愛が欲しかっただけなのに――こんなにも身を削ってきたのに、まだ足りないの?
どうして最後のこのわずかな尊厳すら、こんなにも踏みにじられなきゃいけないの!
その夜は、ひどく長かった。
結月は目を開けたまま、一晩中眠れなかった。
……
翌朝。北川剛直は、窓の外から射し込む眩しい陽射しで目を覚ました。
眉間を揉みながら目を開けると、化粧台の前に座る結月の背中が目に入った。
昨夜の出来事が突然脳裏をよぎり、何かに気づいた彼は黒い瞳を鋭く細め、その全身から冷気が立ち上がった。
背を向けていた結月にも、彼の張りつめた空気がはっきりと伝わってくる。
彼女は何事もないふりをしてスキンケアを続けていたが、突然手首を強く掴まれ、乱暴に立ち上がらされた。
手からスキンケア用品が落ち、ガラス瓶が粉々に砕けて、白いクリームが床一面に広がった。
怒りを込めて顔を上げた彼女だったが、彼の怒りと嫌悪に満ちた黒い瞳と視線が合った瞬間、心がひどく震えた。
「薬なんか盛って、俺に触れさせれば、本物の北川家の妻になれるだと思ったのか?」
剛直は上から見下ろすように、ほとんど歯を食いしばって彼女を睨みつけた。手を離すことなく、さらに強く握り締めた。
その美しい顔立ちは、怒気によって恐ろしいほど歪んでいた。
薬を?
結月は蒼白な笑みを浮かべる。「あなたの目には……私って、そんな女に見えるの?」
剛直は口元に皮肉な笑みを浮かべ、目には強烈な嫌悪の色が宿っていた。「そもそも、あんたは手段を使って明爺様を騙したから、俺はあんたと結婚せざるを得なかったんだ。今さら何を装ってる。」
「お前なんて、みやこの足の小指にも劣る、下賤な女だ!」
下賤な女。清純を装う…
彼の心の中で、自分はこんなにも価値のない存在だったのか。
もし薬でどうにかできたなら、とっくにそうしていたはず。なぜ、こんなにも苦しみながら今まで待ったと思ってるの? 北川剛直は、彼女のことを一ミリも理解していなかった。
3年間の努力も、思いやりも、献身も―全部、無意味だったんだ。
それなら、もう…頑張る必要なんてない。
結月は手首の痛みを堪えながら、力を込めて彼の手を振り払った。
そして顔をしっかりと上げ、揺るぎない声で告げた。
「北川剛直、私たち――離婚しましょう。」
 GOOGLE PLAY
GOOGLE PLAY
/0/17126/coverbig.jpg?v=c284a537dace42787d987069265d4245)

/0/16912/coverbig.jpg?v=6094500432b1f7394a537c696ae01d2f)
/0/16871/coverbig.jpg?v=41d448583624096a3538ad44241991a3)
/0/16915/coverbig.jpg?v=89ed53f6c82d5aef26b777477a92c084)
/0/1217/coverbig.jpg?v=def0503074338784a1a0a4beb2a81d34)
/0/17055/coverbig.jpg?v=572f2f1945fcfe3d6eefc25a610450e5)