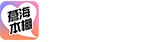浴室のほうから、しとしととシャワーの音が聞こえてくる。その中にいるのは、彼女が密かに結婚してもう二年になる夫――そして、会社での直属の上司でもある、藤原グループの社長・藤原誠司だった。
そもそもの始まりは、一度の酒の席での出来事。入社して間もない頃、酔いに任せて、彼と一夜を共にしてしまった。
その後、誠司の祖父が突然倒れた。彼は「結婚した姿を祖父に見せたい」と言って、偽装結婚を提案してきた。
二人は婚前契約を結び、社内では秘密の夫婦関係を演じることになった。契約はいつでも破棄できる条件で。
明澄は、まさかこんな大きな幸運が自分に舞い込むなんて――夢にも思わなかった。
八年越しの片想いの相手と結婚できるなんて、信じられないほどの奇跡。彼女は迷うことなく、その申し出を受け入れた。
結婚後、誠司は多忙を極め、月の半分以上は姿を見せなかった。
しかし二年もの間、彼の身近に他の女性の気配すらなかった。浮き足立つような噂も、一片さえ立ち上がらなかった。
少し冷たいところはあるけれど、それを除けば藤原誠司はまさに理想の夫だった。
明澄は、手のひらに握りしめた妊娠検査の報告書を見つめながら――甘くて、不安な気持ちで胸がいっぱいになっていた。
彼に伝えようと決めた!
それからもう一つ、どうしても伝えたいことがあった。実は、二年前が初めての出会いなんかじゃない。彼女は十年も前から、ずっと彼を想い続けていたのだ――
バスルームの水音が、次第に静まっていく。
ちょうどその時、誠司のスマホが鳴った。彼は腰にバスタオルを巻いただけの格好でベランダに出て、電話を取った。
明澄が時計を見ると、もう日付はとうに変わっていた。
なぜだか胸騒ぎがした。こんな夜更けに、一体誰からの電話なのだろう?
通話を終えた誠司が戻ってくる。まるで気にも留めない様子で、腰のバスタオルを外した。
彼の身体は驚くほど整っていた。引き締まった腹筋はまるで彫刻のように美しく、全身の筋肉には無駄がない。長い脚と引き上がったヒップ、そのすべてが、あまりにも官能的だった。
何度肌を重ねた仲だとはいえ、明澄の頬は真っ赤に染まり、胸の鼓動は抑えきれなかった。
誠司はベッド脇まで来ると、シャツとスラックスを手に取り、さっと身に着けた。長い指先でネクタイを締めるその所作も、隙がない。
整った顔立ちは陰影まで美しく、どこか気品をまとっていて――目を奪われるほど、完璧だった。
「もう休めよ」 彼はそう言った。
出かけるつもり……?
明澄の胸に、かすかな失望が広がった。手に握りしめた妊娠検査の報告書を、思わずそっと後ろに隠す。それでも、迷った末に声をかけた。「もう、こんな時間だよ」
ネクタイを締めていた誠司の手がふと止まり、彼女のふっくらとした耳たぶを指先でつまんでから、唇の端をわずかに上げて言った。「今夜は、眠る気がないのか?」
明澄の頬が一瞬で真っ赤になり、心臓が暴れだす。何か言いかけたその瞬間――彼はすっと彼女から離れた。「いい子にしてろ。まだ用事がある。待たなくていい」
そう言い残し、誠司はそのまま玄関へ向かって歩き出した。
「……宴」
明澄は思わず追いかけ、背中に呼びかけた。
誠司が振り返る。シャープな顎のラインが月明かりに映え、その視線はまっすぐ彼女を射抜いてくる。
「どうした?」
その声には、外気の冷たさがほんのり混じっていた。言葉の温度が、少しだけ下がったように感じられた。
明澄の胸の奥が、なぜだかぎゅっと詰まるように苦しくなった。けれど、静かな声で尋ねる。
「明日……一緒におばあちゃんに会いに行ける?」
祖母の体調は思わしくない。できれば、誠司にも顔を見せて安心させてあげたかった。
「明日になってから考える」 誠司は、約束もしなければ、否定もせず、そのまま出て行った。
明澄はシャワーを浴びたあとも、なかなか眠れずにベッドの中で何度も寝返りを打った。
どうしても眠れず、仕方なく起きて、温かいミルクを一杯作った。
ふとスマートフォンの画面を見ると、芸能ニュースの通知が届いていた。
こういうニュースには興味がない。閉じようとしたそのとき――ふと、見慣れた名前が視界に飛び込んできた。
#EVの人気デザイナー・小林雪乃が帰国 謎の恋人と空港でツーショット#
記事には、小林雪乃がバケットハットを被り、謎の男性と共に空港に現れたとある。写真の中の男性は顔がはっきり映っていないものの、スタイルの良さは一目でわかる。
明澄はその写真を指先で拡大した。次の瞬間――頭の中に、鈍い衝撃音が響いた。
あのシルエットは――藤原誠司だった。
ということは……今日の午後、急に会議をキャンセルしたのは、小林雪乃を迎えに行くためだったのか?
その瞬間、明澄の胸に、重たい石がぎゅっと押し込まれたような苦しさが広がった。息苦しくて、思わず胸を押さえてしまう。
震える指先のまま、どうしたのか、自分でもわからないうちに――誠司の名前をタップして、電話をかけてしまっていた。
明澄は動揺しながら電話を切ろうとした。だが、そのとき相手の声が届いた。
「もしもし――」
女の声は、とても優しかった。
明澄は一瞬、動きを止めた。次の瞬間、彼女は勢いよく携帯を放り投げた。
そして、胃がかき乱されるような強烈な吐き気に襲われ、堪えきれず洗面所へ駆け込んだ。嘔吐は止まらなかった。
……
夜が明けて。
明澄は、いつも通り会社に向かった。
誠司と電撃結婚した当初、彼は彼女に家庭に入ることを望んでいた。しかし、明澄は自立を望んだ。
誠司はしぶしぶそれを受け入れたが、他所で働くことは認めず、自分の傍に置いて小さな補佐をさせていた。実際のところ、彼女の仕事はお茶を淹れたり雑務をこなしたりする程度だった。
重要な案件は、すべて特別補佐の洲崎牧人に任せていた。
会社の中で、明澄の正体を知っているのは洲崎ただ一人だった。
藤原グループの社長室では、これまで男性アシスタントしか採用されたことがなかった。そんな中、ここ2年間唯一の女性として残っているのが明澄だった。そのため社内では密かに囁かれていた――明澄と藤原社長の関係は、単なる上司と部下以上のものなのかもしれない、と。
だが、時が経つにつれて誰もが気づき始めた。藤原社長は、明澄に対して特別な態度をとることがまるでなかったのだ。それがかえって社内の彼女への目を冷たくさせた。
色仕掛けで取り入ったところで、長く続くはずがない――そんな軽蔑の眼差しが向けられていた。
そのとき、同僚が一枚の書類を手渡しながら、「これ、社長室に届けてくれない?」と頼んできた。
昨夜、宴は帰宅しなかった。そして彼が帰らなかったあの夜、明澄もまた一睡もできずにいた。
電話の向こうにいたあの女は――誰? まさか、彼と一晩一緒に過ごしていたの?そんな疑念が頭の中を渦巻く。
答えはもう、ほとんど見えていた。それでも、彼女は認めたくなかった。認めたら、崩れてしまいそうで……
人は結局、痛い思いをしないと目が覚めないのかもしれない。
今の彼女の心は、嵐のあとの海のように静かだった。明澄は思った――もう、どうなってもいい。ただ、ひとつの答えが欲しい。それが、十年の片想いに終止符を打つための最後の一歩になるのだから。
彼女は落ち着いた様子でエレベーターのボタンを押し、上階へ向かった。降りる直前には髪を軽く整え、自分の状態が万全であることを確かめた。
藤原社長室の前にたどり着いたそのとき、少し開いたマホガニーの扉の隙間から聞こえてきた男の声に、思わず立ち止まる。
「お前、本当に明澄さんのこと、好きなのか?」
話していたのは誠司の幼なじみ、河合延真だった。
「何が言いたいんだ」誠司の声は冷たく澄んでいた。
河合は小さく舌打ちした。「俺は明澄さん、いい子だと思うけどな。お前の好みじゃないのか?」
「なら、お前に紹介してやるよ?」男は軽く投げるように返した。
「やめとくよ」
部屋の中から聞こえてきた河合の嘲るような笑い声が、ひどく耳に刺さった。
彼らは彼女のことを、まるで何かのモノでも扱うかのように語っていた……
明澄の呼吸が一瞬詰まる。資料を握る手に力が入り、ひんやりとした汗が掌ににじむ。
ほどなくして、再び河合延真の声が聞こえた。
「雪乃さんのあの報道のスキャンダル相手って……お前だろ!」
「ああ」
「へえ、お前もずいぶん必死だな。彼女を喜ばせるためなら、何でも差し出すってわけか」
河合は感慨深げにそう言い、さらにからかうように続けた。「昨夜は雪乃さんとずっと一緒だったんだろ?久々の再会でまるで新婚みたいだったんじゃないか?もしかして……ヘヘ、ってさ」
その瞬間、明澄の頭上に雷鳴が轟いたようだった。
顔から血の気が引き、身体の芯まで凍りつくような冷たさが全身を包み込む。
一夜――!
久々の再会でまるで新婚みたい!
一文字一文字が刃となって、明澄の胸に深く突き刺さった。
頭の中では無数の声が渦巻き、叫び合い、視界がぐらりと揺れる。目の前の景色がぼやけていき、音も、遠く、霞んで聞こえなくなっていく。
この場から逃げ出したい――そう思った瞬間、カチャ、と音を立てて扉が開いた。
「明澄さん?」
 GOOGLE PLAY
GOOGLE PLAY
/0/18034/coverbig.jpg?v=63ff8b3a25ffd30a75f58fd39800ca48)

/0/17451/coverbig.jpg?v=b6704e32b9abf8fe5a82110c88522c4e)
/0/17004/coverbig.jpg?v=9d34d2b07e68e891ef48c799177edf59)
/0/18516/coverbig.jpg?v=c846f90bdab438a2b216391532711a43)
/0/18577/coverbig.jpg?v=a6de43246cdb8ad59c63627217d38f24)
/0/17333/coverbig.jpg?v=ab8c582413ed19a11aae8a8cc2a391b3)