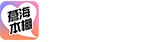誰もが知っていた。彼は一流の婦人科医でありながら、女には一切近づかないことで。 どれだけ若く瑞々しい身体が目の前にあろうと、視線ひとつ上げることはなかった。 私はずっと自分だけは特別だと思い込んでいた。けれど、共に過ごした10年の間、彼は私に触れることを許さなかった。 私の指先が偶然に衣の端へ触れただけでも、 返ってくるのは冷たく硬い一言――「規律を守れ」。 またしても彼の寝床に近づこうとして拒まれたその夜、彼は私の前に10人の男を並べ、順に私を抱かせた。 その後、私は泣きながら彼を責め、拳で叩いた。けれど彼の声はただ平板だった。 「いつまでも未亡人のようにさせるわけにはいかないだろう」 11度目、彼に用意された男が私を押し倒したとき、私は狂ったように睡眠薬を200錠飲み干した。 次に目を覚ましたとき、彼は初めて私の触れ方を受け入れた。 私はそれをきっかけに、少しずつ心を溶かせると信じた。 だが翌日、彼の所有する別荘で、私は彼がある女を腕に抱き、 髪に口づける姿を目にしてしまう。その眼差しには、私が一度も見たことのない熱が宿っていた。 問いただす私に、彼は冷ややかに言い放った。 「彼女はお前とは違う。汚れた下心なんて持っていないし、男を誘惑することもない」 私は唇を強く噛みしめ、血の味が広がるまで堪えた。 「……もういい。私たちは終わりにしましょう」
目次
第1章この五年、私の完敗だった
産婦人科医の権威である周時衍が、女に興味を示さないことは、社交界では誰もが知る事実だった。
どれほど若く美しい肉体が診察台に横たわろうと、彼が目を向けることはない。
それでも私は、自分だけは特別だと思い込んでいた。共に過ごした十年、彼は私に指一本触れることを許さなかったというのに。
偶然、私の指先が彼の服の裾を掠めただけで、
氷のように冷たい声で「弁えろ」と一喝されるのが常だった。
また彼のベッドに忍び込もうとして失敗した夜、彼は十人もの男を呼び、私を辱めた。
事が終わった後、私が泣きながら彼を殴っても、ただ平然と「お前を一生独り身にしておくわけにもいかないだろう」と言い放つだけだった。
十一人目の男にベッドへ押さえつけられた時、私はついに狂い、二百錠の睡眠薬を飲み下した。
再び目を覚ますと、周時衍は柄にもなく、私が触れることを許した。
これで少しは彼の心を溶かせるかもしれない――そんな淡い期待を抱いたのも束の間だった。
翌日、彼のプライベートな別荘で、一人の女性を腕に抱く彼を目撃してしまったのだ。
彼はその女性の髪に口づけを落とし、その瞳には、私が一度も見たことのない熱が宿っていた。
私が問い詰めると、周時衍は冷たい表情で言い放った。
「語棠は君とは違う。彼女はそんな汚らわしい考えを持たないし、男を誘惑したりもしない」
血の味が滲むまで、私は唇を強く噛み締めた。
「もういいわ、周時衍。私たち、別れましょう」
......
病室の外からは、周時衍と彼の特別な女性――蘇語棠の甘い囁き声が聞こえてくる。
病室の中では、胃洗浄を終えた私が、痛みで眠れずに呻いていた。
周時衍はかつて、自分の愛する人が他の男に汚されることは決して許さないと言っていた。
だが、私が純潔を守るために睡眠薬を飲み、十時間にも及ぶ救命措置の末に意識を取り戻した時、彼が残した言葉は「自業自得だ」の一言だけ。
その一方で、彼の特別な女性が街で転びそうになり、後ろにいたボディガードが咄嗟に支えただけで、そのボディガードの手を切り落とそうとするほどの執着を見せる。
その時、私はようやく悟った。私が彼の愛する人ではなかったのだと。
ドアの向こうから漏れ聞こえる睦言は、まるで無数の針となって私の心を突き刺した。
やがて、事を終えた周時衍が冷たい顔で部屋に入ってきた。
彼は苛立たしげに私を見据える。「また別れるだと? 今月で何度目だ。いい加減にしろ」
彼の腕の中にいる蘇語棠は、まるで野良猫のように挑発的な視線を私に向けた。「林晚お姉さんが嫌なら、それでいいわ。ちょうど病院にいることだし、この子、堕ろしてくるから」
「妊娠……したの?」私は呆然とした。
三年前、子宮内膜に嚢腫が見つかった。医師は、がん化する前に妊娠・出産しなければ、一生母親にはなれないと告げた。
私が地面に膝をついて彼に懇願しても、彼は決して私に触れようとはしなかった。
それなのに、蘇語棠が帰国してわずか一ヶ月で、彼は彼女を妊娠させたのだ。
心臓が張り裂けそうな痛みで、息もできない。胃洗浄の激痛さえ、霞んでしまうほどだった。
周時衍は蘇語棠の腹部を庇うように手を添えた。「彼女のことは気にするな。どうでもいい人間だ。君はただ、体を大事にすることだけを考えろ。あとは全部、俺に任せろ」
その最後の言葉は、五年前、彼が私に言った言葉とまったく同じだった。
彼は外科の主席執刀医だった。あの日、彼を妬む何者かが、彼の右手をメスで切り刻もうとした。
私は彼を庇って五度斬りつけられ、彼にはかすり傷一つ負わせなかった。
手術室から命からがら戻ってきた私を、彼はベッドの傍で抱きしめ、こう誓ったのだ。
「晚晚、この手は俺の第二の心臓だ。君は俺を救ってくれた。だから俺は、生涯をかけて君を守る」
「君を守る機会をくれないか。結婚してくれ!」
彼が私に永遠を誓ったのは、今いるこの病室だった。はっきりと覚えている。
しかし今、ここにあるのは冷え切った視線と、嘲りだけだ。
心の奥底にあった最後の希望が消え去った。蘇語棠の首筋にある無数の赤い痕を見て、私はか細い声で言った。「本気よ。離婚しましょう」
途端に、周時衍の顔が険しくなる。
「ああ、いいだろう。消えるならとっとと失せろ。地の果てまで消えちまえ。二度と犬みたいに、尻尾を振って俺の元へ戻ってくるな」
言い終えると、彼はドアを叩きつけるように閉め、蘇語棠を抱いて出て行った。
鼻の奥がツンとする。この五年、周時衍との関係において、私は何もかもを失った。完全な敗北だった。
おすすめ
/0/17058/coverbig.jpg?v=4ee2c2e8259a00e8d1ac9e2201018eaa)
この恋が、私の人生を壊した
水無月 ほのか容姿も才能もあり、人生の勝者だと思っていた——氷川詩織は、そう信じていた。 けれど気がつけば、彼女の手札はすべて崩れ去っていた。 中絶、容姿の損壊、仕事の失墜、名誉の破壊——何もかもが壊れていった。 なぜ、こんなことになったのか。 きっと、あの男——一条慎との恋が始まりだった。 愛は人を救うはずだったのに、彼女にとっては地獄の扉だった。 ——これは、一人の女が「愛」を代償に、何を失ったのかを描く痛切な記録。
/0/17002/coverbig.jpg?v=0b4e688e123ea329465cd41ab25b6a94)
離婚してから、私が世界一の女になった話
空木 アリス三年間、献身し尽くした神谷穂香に、葉山律は一度も心をくれなかった。 だから彼の“白月光”のため、潔く離婚届を差し出した。 豪門たちは嘲笑う。「穂香、どうして、葉山社長と離婚したの?」 穂香は笑って返す。「家業の数千億を継ぐから、彼じゃ釣り合わないの」 誰も信じなかった——翌日、世界最年少の女富豪として彼女の名前が報道されるまでは。 再会の場で、彼女を囲む若い男たちを見た葉山律は顔を曇らせて言う。 「俺の資産も全部やる。戻ってきてくれ、穂香…!」
/0/17332/coverbig.jpg?v=ccb99d3220a8db315143e23210439794)
離婚したら、元夫が知らなかった私が目を覚ました
桜井 あんず「君なんて最初から必要なかった」 夫の冷たい一言で、榛名文祢の四年間の結婚は幕を閉じた。 家族のための政略結婚、心の中にいるのは宝木理紗だけ――そう告げられた彼女は、静かに立ち去る。 だが、去ったのは黒岩奥様であり、帰ってきたのは業界を震撼させる実力派カリスマ。 華やかな舞台で輝きを放つさくらを見て、前夫は戸惑い、嫉妬し、そして……気づく。 「君は最初から、誰よりも眩しかった」 けれどその隣には、すでに新たな男がいて——?
/0/17004/coverbig.jpg?v=9d34d2b07e68e891ef48c799177edf59)
フラれた翌日に結婚したら、億万長者の妻になってました
緋色 カケル失恋の翌日、勢いで見知らぬ男と結婚した七瀬結衣。 どうせすぐ破産すると言う彼を支えるつもりだったが——なぜか彼は異常に頼れる。 ピンチのたびに現れては完璧に解決。どう見ても“運だけ”じゃない! 実はその正体、世界一の大富豪・朝倉誠司。 「これが君の“運の良さ”だよ」 ——波乱のスタートだった“契約結婚”は、いつしか本物の愛へと変わっていく。
/0/16915/coverbig.jpg?v=89ed53f6c82d5aef26b777477a92c084)
追い出された果てに、億の愛が始まる
藤宮 あやね20年間尽くした水野家に裏切られ、追い出された恩田寧寧。 「本当の親は貧乏だ」——そう思われていたが、その実態は海城一の名門。 億単位の小遣いに、百着のドレスと宝石、そして溺愛されるお嬢様生活。 彼女を侮っていた“元・家族”たちは、次々と彼女の真の素顔に震撼する—— 世界一の投資家、天才エンジニア、F1級のレーサー!? そんな彼女を捨てた元婚約者が、なぜか突然「やっぱり好きだ」と告白? でももう遅い——“本物の兄”とのお見合いが始まってるのだから。
/0/17136/coverbig.jpg?v=6593f5ef791a64cafc1bbc3591873a03)
離婚された女の正体が、世界最強の『三重スパイ』だった件
時計塔 リリス三年間、ただ彼のために料理を作り、素性を隠し、尽くし続けた小鳥遊音羽。 だが返ってきたのは、冷たい離婚届。 愛も希望も踏みにじられたその日、彼女は静かに立ち去った—— そして、世界は震える。 香水界の天才、諜報界の影の女王、ハッカー帝国の後継者—— 全ての“正体”が彼女だったなんて。 元夫・東條司が気づいた時にはもう遅く、彼女の隣には謎多き男・風間慶一がいた。 「追いかける?……その資格、君にあるのか?」 ——これは、真の彼女を知らなかった者たちが後悔する、逆転と覚醒のラブストーリー。
トップ
 GOOGLE PLAY
GOOGLE PLAY
/0/19227/coverbig.jpg?v=fb49b7766ef51816cbf46580d61f634d)