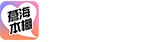私の夫は世界的に名高いトップクラスの調教師で、誰もが知る珍獣動物園を経営している。 どんな獰猛な野獣であっても、彼の前では猫のようにおとなしくなる。 だが――あの日。夫が息子を連れて動物園を案内していた時、最も可愛がっていたライオンが突然檻を破って飛び出し、息子をひと口で飲み込んだ。 霊安室で、息子の残された体を抱きしめて泣き崩れる私。一方の夫は、その夜のうちに動物園へ戻り、怯えたライオンをなだめていた。 「いつもはおとなしい子なんだ……今回はただの事故だよ」 「人にはそれぞれの運命がある。残念だが、もう戻らないんだ。前を向こう」 ――けれど、監視カメラで私は見てしまった。新しく入った女性管理員を抱き寄せ、夫がささやく姿を。 「君のせいじゃない。檻の修理が遅れたのは仕方ないさ。ここでは誰もが怪我をする可能性がある。ただ、あの子は運が悪かっただけだ」 その瞬間、私の血は凍りついた。 息子を死なせた元凶は――彼自身だったのだ。 監視カメラを閉じた私は、夫が誇りにしていたあのライオンを国家動物園に寄贈した。 そして、裏社会で生きる108人の兄たちへ、息子の遺影を一斉送信した。 「血の代償を、必ず払わせる」
目次
第1章始まり
夫は世界的な名声を持つトップクラスの猛獣使いで、世界的に有名な珍奇動物園を経営している。 どれほど凶暴な野獣も、彼の前では猫のように従順になる。
しかし、彼が息子を連れて動物園を案内したあの日、彼が最も可愛がっていたライオンが突然檻から飛び出し、私たちの子を一飲みにした。
霊安室で、私は息子の無残な体を抱きしめて気を失うほど泣き叫んだが、彼はその夜のうちに動物園へ戻り、怯えたライオンを慰めていた。
「若若、あの子ライオンは普段はとてもおとなしいんだ。今回はまったくの事故だ」
「人にはそれぞれ運命がある。俺も残念だが、亡くなった者は戻らない。俺たちは前を向かないと」
監視カメラの映像を見るまでは。そこで彼は、新入りの女性飼育員を抱きしめ、優しく慰めていた。
「小茹、君が檻の破損を時間通りに報告しなかったせいじゃない。動物園では誰もが怪我をするリスクを負っている。ただ年年の運が悪かっただけだ」
その瞬間、全身の血が凍りついた。
息子を殺したのは、彼が最も崇拝する父親その人だったのだ。
監視カメラの電源を切り、私は彼が誇りにしていた「あの子ライオン」を国立動物園に無償で寄付した。
続いて、裏社会に通じる百八人の兄たちに、息子の遺影を一斉送信した。
【奴らに血の償いをさせて】
……
寄付の通知を送った途端、携帯が鳴った。
「許若!貴様、気でも狂ったか!? 国際巡業の招待状まで送ったのに、あの子ライオンを寄付しただと? あれがいなきゃ、誰がこんなオンボロ動物園に来るんだ!」
「息子が死んで辛いのはわかる。だが俺に何の関係がある? あいつが自分で運が悪かっただけだ!なんで俺と霜霜に八つ当たりするんだ?」
「二十四時間やる。申請を取り下げろ。 さもなければ離婚だ!」
怒鳴り散らした後、江澈は乱暴に電話を切った。
私は携帯を握りしめ、声もなく涙がこぼれ落ちた。
喧嘩のたびに彼は離婚を切り札にし、そのたびに私は例外なく折れてきた。だが今日、私はもう疲れてしまった。
江澈は幼い頃から動物が好きで、周りからは変人扱いされ、いじめ抜かれてきた。挙句の果てには集団リンチで失明し、絶望の淵にいた。
旅行中だった私が彼を救い、哀れに思って、持てる人脈をすべて使って角膜を探し出し、彼が夢を追えるようにしたのだ。
視力を取り戻した彼は私に深く感謝し、九十九回プロポーズしてきた。昼夜を問わず動物の世話をし、動物園を軌道に乗せた後、ようやく私の一族は彼との結婚を許した。
結婚後、彼は先天性の乏精子症と診断され、医者からは生涯子供は望めないと宣告された。
私は運命を信じず、彼と七年間体外受精を試み、腹部が青紫のアザだらけになるまで注射を打ち続けた。
そうしてようやく、一つの胚が着床したという知らせを得たのだ。
子供が生まれた日、彼は狂ったように喜び、私のお腹を撫でながら泣き笑いした。
私たちを絶対に幸せにすると、固く誓った。
あの頃、私たちは確かに幸せだった。
呉霜が現れるまでは。
……
私は涙を拭い、あの監視カメラの映像をネットに公開しようとした。
だが、携帯の画面は真っ暗だった。
何者かが、あの決定的な映像を削除したのだ。
しかし、代わりに別の動画メッセージが届いた。
それを見て、私は怒りで全身が震えた。
「お嬢様、大丈夫でございますか?」執事が心配そうに尋ねた。
私は深呼吸する。「動物園へ。今すぐ。 監視カメラを必ず復旧させて」
車が園内に入ろうとした矢先、門の外に横断幕を掲げた黒山の人だかりが見え、怒号が天を突いていた。
数十人が「仕事を返せ」「資本家は出ていけ」といったスローガンが書かれたプラカードを怒りに任せて掲げている。
私の心臓がどきりと沈んだ。
江澈は一番高い場所に立ち、スーツをきっちりと着こなし、見るからに心を痛めたという表情を浮かべている。
その隣には、あの若い女性飼育員の呉霜がおり、目を赤くして涙を拭っている。
「停めて」と私は執事に告げた。「張さん。 あなたは先に運転手さんと従業員用通路から入って、監視カメラの復旧をお願い。私は様子を見てくる」
私が車を降りた途端、腐った野菜の葉が肩に叩きつけられた。
「あいつだ!あの毒婦が動物園を閉鎖しようとしてるんだ!」 いかつい顔の中年女性が、私を忌々しげに指差した。
「この悪徳資本家め!なんで動物園を閉鎖するんだ!動物園はみんなのものだ!全員が心血を注いできたんだぞ!」別の男が拳を振り上げた。
「金持ちは冷血だ。自分の子供が死んだからって、全員を道連れにする気か!」
怒り狂った群衆が、津波のように私に押し寄せてくる。
全員、江澈の故郷の親戚たちだ。
どうりで最近、多くの動物が弱々しいわけだ。彼は私の雇った優秀な飼育員たちを解雇し、そのポストをすべて自分の身内に分け与えていたのだ。
江澈は高台に立ち、見え透いた冷笑を口元に浮かべ、私を助けようとする素振りも見せない。
あの日、私が匿名でこの園を設立し、彼を園長に据えたのは、動物好きな彼に仕事の機会と「後ろ盾」を与えたかったからだ。
私に釣り合わないと、彼が終始不安に苛まれることのないように。
わざわざ世界中に散らばる裏社会の兄たちに頼んで珍しい動物を運び込ませ、トップクラスの調教師たちに裏で管理させていた。
彼は自分に天賦の才があると信じ込んでいるが、彼が手なずけたとされる猛獣たちが、とっくの昔にプロのチームによって調教済みだったことなど知りもしない。
今や江澈は世界的な猛獣使いとなり、動物園も国家級の5A観光名所になった。
彼は天狗になり、動物園が今の地位にあるのは完全に自分の手柄だと信じ込み、
この私――陰の最大出資者――のことまで鼻であしらうようになった。挙句、私の金で呉霜という「第三者」まで雇い入れたのだ。
園内でどれだけの動物が死んでいるか、彼は陰で知りもしない。私が兄たちに頼み、彼が死なせた分を夜通し新しい個体と補充させていたからだ。
誰もが私という「専業主婦」は、江澈という金の生る木から一生離れられないと思っている。
だが彼らは知らない。江澈の成功は、完全に私の「施し」によって成り立っていることを。
私がいなければ、彼は何者でもない。
「皆さん、落ち着いて!」私は声を張り上げた。「動物園は閉鎖しません。ただ……」
「ふざけたこと抜かすな!」 江澈の従弟が群衆から飛び出してきた。「兄貴から聞いたぞ!このキチガイ女が動物園を寄付するってな!そうなったら俺たちの住宅ローンや車のローンはどうなるんだ? 子供の学費は!? あんたらにとっちゃ、この動物園はただの小さい商売かもしれねえが、こっちは家族を養うための仕事なんだよ!」
その一言が、騒動を一瞬にして暴動に変えた。
誰かに突き飛ばされ、私はよろめきながら数歩下がり、背中をフェンスに打ち付けた。
その時になってようやく、江澈が私の前に立ちはだかった。
おすすめ
/0/19220/coverbig.jpg?v=e8f8523ce94360559d1d4fc3440d2b7b)
冷遇令嬢、実は天才。婚約破棄した彼らにざまぁ!
田中 翔太桜井陽葵は家族から愛されない「無能で醜い女」とされていた。一方、継母の娘である山口莉子は才色兼備で、間もなく名門一族の後継者・高木峻一と結婚することになり、栄華を極めていた。 人々は皆、強い者に媚びへつらい、弱い者を踏みつけた。山口莉子は特に傲慢で、「桜井陽葵、あなたは永遠に犬のように私の足元に踏みつけられるのよ!」と高らかに言い放った。 しかし、結婚式当日。人々が目にしたのは、豪華なウェディングドレスを纏い、高木家に嫁いだ桜井陽葵の姿だった。逆に山口莉子は笑いものにされる。 街中が唖然とした。なぜ!? 誰もが信じなかった。栄光の申し子・高木峻一が、無能で醜いと蔑まれた女を愛するはずがない。人々は桜井陽葵がすぐに追い出されるのを待ち続けた。 だが待てども待てども、その日が来ることはなかった。現れたのは、眩い光を放つ桜井陽葵の真の姿だった。 医薬界の女王、金融界の大物、鑑定の天才、AI界の教父――次々と明かされる正体の数々が、嘲笑していた者たちの目を眩ませた。 汐風市は騒然となった! 山口家は深く後悔し、幼なじみは態度を翻して彼女に媚びようとする。しかし桜井陽葵が返事をする前に――。 トップ財閥の後継者・高木峻一が発表したのは、桜井陽葵の美しい素顔を捉えた一枚の写真。瞬く間に彼女はSNSのトレンドを席巻したのだった!
/0/17333/coverbig.jpg?v=ab8c582413ed19a11aae8a8cc2a391b3)
契約妻を辞めたら、元夫が泣きついてきた
藤宮 あやね冷徹な契約結婚のはずが、気づけば本気になっていた―― 藤沢諒との結婚生活で、神崎桜奈はただひたすらに尽くしてきた。 だが火災の夜、彼が守ったのは「初恋の彼女」。 心が砕けた彼女は静かに家を去り、すべてを捨てて離婚届に判を押す。 ……数ヶ月後、彼女は別人のように華やかに輝いていた。 恋敵たちが列をなす中、彼は懇願する。「君がいないとダメなんだ、やり直そう」 その言葉に、彼女は微笑む――「再婚希望?じゃあ四千万円から並んでね」
/0/17054/coverbig.jpg?v=06e55400a34e82013850ebca438b7142)
別れの日、あなたの瞳は彼女を映していた
氷堂 ユキ古川結衣と藤原翔太は、誰にも知られぬまま三年間の秘密の結婚生活を送っていた。 彼のそばにいられるだけで十分だった――そう思っていた彼女が、妊娠を知ったその日。 目の前に映ったのは、夫と彼の「初恋」の親密な姿だった。 すべてを胸にしまい、彼女は静かに姿を消す。 しかし数ヶ月後、膨らんだお腹で再会したふたりの運命は、静かに、そして激しく動き出す——。
/0/19492/coverbig.jpg?v=59a649afd3191d97cc9c34bed8aea3e3)
裏切り夫を見捨てた妻、今は億万長者ママです
風間 彩榛葉璃奈は、行く当てもなく、ある取引に身を委ねた。 ホテルで彼女を激しく求めたのは、非情にも別れた元夫だった! 彼は、忘れられない女性の仇を討つため、彼女の家族を破産に追いやり、さらには愛人契約を彼女の顔に叩きつけて侮辱した。 榛葉璃奈は弟を救うため、妻から愛人となり、昼は彼の「忘れられない女性」に嫌がらせをされ、夜は彼の下で溺れる日々を送る。彼女が耐え忍ぶのは、ただ真相を明らかにするためだった…… 後に、佐久間修哉はその女性が彼女をビルから突き落とすのを、冷ややかに見つめていた。 数年後、榛葉璃奈は子供を連れて華麗に舞い戻る。億万長者となった彼女は猛反撃を開始し、元夫を破産に追い込んだ! プライドの高かった男は魂が抜けたように、目を赤く腫らし彼女を壁際に追い詰める。「璃奈、俺が悪かった。やり直そう!」 榛葉璃奈は彼の宿敵の腕を取り、冷たく艶然と微笑む。「元旦那様、消えてくださる?私の幸せな家庭生活の邪魔をしないで」 佐久間修哉は彼女の腕に抱かれた自分そっくりの子供を見つめ、後悔の念に泣き崩れた!
/0/17056/coverbig.jpg?v=9227dfb69cc5978720f33d660f45dd47)
月島璃子、その正体、すべて伝説
月城 セナ二十年育てられた家から、突然「あなたは本当の娘じゃない」と追い出された月島璃子。 薬を盛られ、金づるにされかけた彼女は逃げ出し、捨てられるように田舎へ送り返される——が、 待っていたのは、豪邸に住む日本一の資産家・鳳城家の本当の娘としての人生だった。 絵画界の幻の巨匠、医術の天才、音楽界の革命児、IT業界の伝説——そのすべてが、実は“彼女”。 見下していた義妹たち、後悔する元家族、そして……彼女の正体に気づいた京城一の御曹司が囁く。 「もう“奥様”って呼ばせてくれ。俺の妻になるのは、君だけだ」
/0/17451/coverbig.jpg?v=b6704e32b9abf8fe5a82110c88522c4e)
「さよなら」を告げたのは、あなたよ?
白鳥 あおい一度は彼にすべてを預けた――若く無防備だった津本薫は、愛よりも欲望にまみれた関係にすがっていた。 だが彼の心にいたのは、帰ってきた“昔の恋人”。 空っぽの部屋、無言の夜、そして別れの言葉と一枚の小切手。 「後会うこともないわ」 彼女はそう言って、涙一つ見せずに立ち去った。 ……数年後、再会した彼女の隣には新たな男性が。 嫉妬に焦がれた彼は、億の財産と指輪を差し出して告げる―― 「列に並ばず、もう一度君のそばにいたい」
トップ
 GOOGLE PLAY
GOOGLE PLAY
/0/19240/coverbig.jpg?v=2b3915210f140960239e90face8a3173)