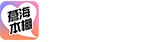私は、とある茶室で特別な茶葉を売っている。 その茶葉を料理に加えると、食べた者は中毒者のように、その禁断の味を求めずにはいられなくなるのだ。 噂を聞きつけた高級料理店の主たちが、後を絶つことなく私の元を訪れる。 だが私だけは知っている。その茶葉が、中毒者たちの鮮血を吸って育つという真実を。
目次
第1章垂涎の茶
私が勤める茶室では、ある特別な茶葉を扱っている。
ひとたび料理に加えれば、その味は食した者を虜にし、病みつきにさせるほどの美味へと変貌する。
噂を聞きつけた高級レストランのオーナーたちが、後を絶たない。
だが、私は知っている。この茶葉が、それに溺れた者たちの血を啜って育つという秘密を。
【1】
私はとある茶室の店員をしている。この店では飲み物は出さず、茶葉のみを、それも紅茶だけを専門に扱っている。
その中に「垂涎茶」と呼ばれる特別な紅茶があった。
その名の通り、この茶葉を料理に加えると、人はよだれを垂らすほどに食欲をそそられ、一度味わえばやめられなくなるという。
その特異性ゆえに、垂涎茶は毎月数量が限定され、購入数にも制限が設けられていた。
価格もまた、目玉が飛び出るほどに高い。
高級レストランのオーナーたちは、数ヶ月、長い時には一年も前から予約を入れ、ようやく一グラムの垂涎茶を手にするのだ。
「黛さん、お忙しいところ悪いね」
現れたのは李社長。うちの店の常連客だ。
「李社長、どうぞお掛けください」私は笑顔で席を勧めた。「本日は茶葉を? 確認いたしましたが、今月はご予約をいただいていないようですが」
李社長は気まずそうに笑みを浮かべた。「そこをなんとか……黛さん、融通を利かせてもらえないだろうか」
私は眉をひそめる。「申し訳ありません、李社長。店の決まりはご存知のはずです」
垂涎茶は毎月十個限定。一個一グラムで、価格は200万円。
さらに、購入はお一人様につき毎月一個までと定められている。
店の予約は常に数ヶ月先まで埋まっている。もし李社長の頼みを聞き入れれば、正規の予約客の分がなくなってしまうのだ。
実のところ、私自身も常々疑問に思っていた。これほどの高値で売れる茶葉を、店長はなぜもっと多く売ろうとしないのだろう。
金が嫌いな人間などいるはずもない。きっと、希少価値を高めるための販売戦略なのだろうと、私は自分を納得させていた。
「今、どうしてもこの茶葉が必要なんだ。黛さん、どうか知恵を貸してくれないか」 李社長は焦ったように椅子から立ち上がった。「金なら上乗せする!頼む!」
私はため息をついた。「私の一存ではどうにもなりません。どうかお引き取りを」
そう言って李社長を店外へ促し、慌てて扉を閉ざした。
扉を叩く音が外から響く。私はやるせなく首を振った。
本当にどうすることもできないのだ。店長の決定に、私は微塵も逆らうことなどできず、ただ従うしかない。
なにしろ、店長は私の命の恩人なのだから。
【2】
私は、店長に拾われた浮浪児だった。物心ついた頃から、ずっと路上で暮らしてきた。
両親の顔も知らず、物乞いや心優しい人々の施しで日々を繋いでいた。
この茶室の前で店長に出会うまでは。彼女は私を拾うと、ちょうど店員が欲しかったのだと言い、この店に住まわせてくれた。
店長は私に良くしてくれた。少なくとも衣食に困ることはなく、毎月給料も支払ってくれる。
私の心の中で、店長はいつしか母親のような存在になっていた。
私にできることは、彼女のためにこの店を誠実に守ることだけだ。
李社長のように、予約もなしに茶葉を懇願しに来る客はこれまでにも大勢いた。私も一度、彼らに少しだけでも売ってあげてはどうかと店長に尋ねたことがある。
その時の店長は、ただ冷ややかに私を一瞥し、氷のような声で言い放った。「あなたは、自分の役目だけ果たしていればいい」
当時の私は愚かにも引き下がらず、こう問い返してしまった。「この茶葉は、それほどまでに希少なのですか? いったいどう育てれば、これほどの価値がつくのでしょう?」
その瞬間、店長の顔色が一変した。私は裏庭へと引きずられていき、容赦なく鞭で打たれた。
返しのある鞭が皮膚を裂くあの痛みは、今思い出しても、古傷が疼くようだ。
翌日、茶室の扉を開けると、戸口にうずくまる李社長の姿があった。
どうやら一晩中、そこにいたらしい。足元には無数の吸い殻が散らばっていた。
私が扉を開けたことに気づくと、彼は血相を変えて駆け寄り、私の腕を掴んだ。「黛さん、君を困らせたいわけじゃない。だが、どうか頼む……」
その剣幕に、私は咄嗟に腕を振りほどき、再び扉を固く閉ざした。
幸い、この先数日は予約客が来る予定はない。彼が諦めるまで、店を閉めておけばいい。
しかし、それから数日間、李社長は店の前から動こうとせず、ついには寝具を持ち出し、そこで寝泊まりを始めたのだ。
このままでは商売にならない。いつまでも店を閉めているわけにはいかない。
私が扉を開けるのを見ると、寝起き姿の李社長が飛び起きてきた。「君が心優しいのは知っている。今回一度きりでいい。葉っぱ一枚だけでも、どうにか工面してくれないか!」
私が黙り込んでいると、彼はさらに畳みかけてきた。「金なら上乗せする!五倍だ!どうだね、黛さん」
そして、私の耳元で声を潜めて囁いた。「この金は、すべて君の懐に入れていいんだ。よく考えてみてくれ」
心が、ぐらりと揺れた。店長は毎月給料をくれる。だが、それは彼女の儲けに比べれば、九牛の一毛に過ぎない。
拾われたばかりの頃は、温かい食事と雨風をしのげる寝床があるだけで、この上なく満たされていた。だが、今は……。
最低限の生活費にしかならない給料では、もう私の心は満たされない。もっと、金が欲しい。
私は、秦靖から譲ってもらった旧式のスマートフォンに目を落とす。そして、意を決して頷いた。
実を言えば、私が垂涎茶を横流しするのを躊躇していたのには、もう一つ理由があった。
店長が茶を店に持ってくる時、茶は重い木箱に鍵をかけて運ばれます。あの茶葉には、どこか禍々しい気配が漂っているのだ。
その木箱は、血の海にでも浸したかのような、不気味な暗い赤色をしていた。そして、届けられたばかりの新鮮な垂涎茶からは……。
いつも、微かな血の匂いが漂ってくるのだ。
嵐山 琳のその他の作品
もっと見る/0/19311/coverbig.jpg?v=324a9a28ca633aaa1fadd0280c29c631)
婚約者の裏切り?問題なし、叔父が甘すぎます
都市[正体隠し+スピード婚+契約結婚からの溺愛+スカッと系ざまぁ] ある名家の令嬢は、20年間も田舎に置き去りにされて育った。都会の実家に戻った矢先、婚約者と家の養女の浮気現場を目撃してしまう。自暴自棄になった彼女は、勢いで婚約者の叔父のベッドへもぐりこんだ。 一夜の気まぐれが、亡き許嫁のために3年間も操を守り続けてきたと噂の男の理性を、いとも簡単に打ち砕いてしまった……。 事後、ストイックで知られるその男は「体だけの関係だ」と言い放つ。腰の痛みに耐えていた彼女は、それを聞いて呆れて笑ってしまった! 「昨夜のあなたの腕前だけど、はっきり言って、満足度はイマイチね。チップは200円、それ以上はびた一文出せないわ!」 男は顔を曇らせ、彼女の腰を掴んで引き寄せる。「昨夜の君の身体は、その口よりもずっと正直だったが?」 なんだかんだで、彼女はあのクズな元婚約者の「叔母」という立場に収まってしまう。 婚約披露宴の席で、偽善者の元婚約者は顔面蒼白になり、彼女に頭を下げるしかなかった! 誰もが彼女のことを、品がなく、教養もない、出来損ないの娘だと噂していた。 しかし、ある超一流の社交パーティーで、彼女は資産1000億の大物として姿を現す。 「私が名家に嫁ぐですって?私自身がその『名家』よ」
おすすめ
/0/18516/coverbig.jpg?v=c846f90bdab438a2b216391532711a43)
泣かないで、もうあなたのものじゃない
白百合まどか結婚して二年、待望の妊娠がわかったその日——彼は冷たく告げた。「離婚しよう」裏切りと陰謀に倒れた彼女は、命がけで子を守ろうとするも、夫は応えなかった。絶望の果てに、彼女は海を越え、すべてを捨てて消えた。数年後、成功者として名を馳せる男が、決して口にできない名を抱き続けていたことを、誰も知らない。——結婚式の壇上で、彼は跪き、赤く潤んだ瞳で彼女を見上げる。「子どもを連れて、誰の元へ行くつもりだ——」
/0/19230/coverbig.jpg?v=10c6a320c6f044ecea6ebedeb48cd253)
彼の裏切りに消えた妻、復讐は百倍返しで
雪代墨(Yukishiro Sumi)裏社会の大物が、財閥令嬢を10年もの間ひそかに想い続け、彼女の家が破産したその日にようやく妻として迎え入れた。 結婚後、彼は彼女を溺愛し、まるで天にまで持ち上げるように大切にした。 彼女は幸せを手に入れたと信じていた――5年目までは。 思いがけず妊娠した時、いつも愛情深かったはずの夫は、子どもを諦めろと迫った。 そして偶然、彼が友人と交わす会話を耳にしてしまう。 浮気をしていたのだ。別の女のために、彼女に流産を強いたのだ。 さらに遡れば、家の破産も、両親の死も、すべて彼の仕組んだ計略だった。 彼女は国外にいる彼の宿敵と手を組み、死を装って姿を消す。 彼女の死を知った男は、泣きながら帰ってきてほしいと懇願した。 だがすべては遅すぎた。彼女が味わった苦しみは、これから何倍にもなって彼に返されるのだから。
/0/17565/coverbig.jpg?v=b4b288b3ac9a609ecb7c6d4203eb3f02)
捨てられ妻、今は大物に抱かれています
霧生 隼裏切り、侮辱、離婚——それでも、柴田友子は再び立ち上がった。........ “ただの主婦”だった彼女は、いまや世界が注目する人気画家。 名声と輝きを手にした瞬間、かつての夫が「やり直そう」と現れる。 だが彼の視線の先には、さくらを腕に抱く謎の大物実業家の姿が―― 「紹介しよう。彼女は“俺の大切な人”だ」 嫉妬と未練、そして本当の恋が交差する、痛快逆転ラブロマンス。
/0/19030/coverbig.jpg?v=e877a57b9a2e6036a02a411287856f2a)
離婚したら、世界が私に夢中になった
中村 健太結婚してからの3年間、彼女は“奥様”としてただ耐え続けた。 愛していたから、どんな仕打ちも我慢し、彼の身の回りを世話し、外での浮ついた噂にも目をつぶってきた。 けれど、彼は最後まで彼女の想いを無視し続けた。彼女の気持ちを踏みにじるだけでなく、自分の妹に命じて彼女に酒を飲ませ、取引相手のもとへ送り込むという暴挙さえ黙認した。 そのとき、彼女はようやく目を覚ました。長年の片想いが、いかに滑稽で、哀れなものだったかに気づいたのだ。 彼にとって、自分はただの“ひとり”でしかなかった。取り巻く女たちと何の違いもなく、ただ近くにいただけの存在にすぎなかった。 彼女は離婚届を置き、後ろを振り返ることなく家を出た。 その後、彼は目の当たりにする。何も持たなかったはずの彼女が、自力で成功をつかみ、人々の憧れの的となっていく姿を。 再会したとき、彼女は堂々としていて、自信に満ちあふれていた。そしてその隣には、すでに別の“大切な人”がいた。 その新しい男の顔を見た瞬間、彼は悟る。彼女がずっと見つめていたのは、自分ではなく、“誰かに似た顔”だったことを── 静かな場所で、彼は彼女の行く手をふさぐ。「……俺を、弄んだのか?」
/0/17054/coverbig.jpg?v=06e55400a34e82013850ebca438b7142)
別れの日、あなたの瞳は彼女を映していた
氷堂 ユキ古川結衣と藤原翔太は、誰にも知られぬまま三年間の秘密の結婚生活を送っていた。 彼のそばにいられるだけで十分だった――そう思っていた彼女が、妊娠を知ったその日。 目の前に映ったのは、夫と彼の「初恋」の親密な姿だった。 すべてを胸にしまい、彼女は静かに姿を消す。 しかし数ヶ月後、膨らんだお腹で再会したふたりの運命は、静かに、そして激しく動き出す——。
トップ
 GOOGLE PLAY
GOOGLE PLAY
/0/19474/coverbig.jpg?v=b6a6ad6fd4b381315ec02feee105b4d9)

/0/17639/coverbig.jpg?v=b10df6d26e351ef19aef34a7d1b9218a)