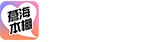敵対する部族のアルファに囚われたその時。 彼はちょうど運命の番と日の出を眺めていた。 誘拐の報せを受けた彼は、淡々とした声で言い放つ。「縛っておけ。少し痛い目を見れば、もう俺に縋りつくこともなくなるだろう」 生死の瀬戸際、選択肢は残されていなかった。 私は敵対部族のアルファに縋りつき、震える声で囁く。「お願い……殺さないで。なんでも言うとおりにするから」 ようやく彼が私を思い出した時には――敵方のアルファが眠り込んだ私の横顔を見下ろし、笑みを浮かべていた。「遅かったな。今の彼女は、とてもお前について行ける状態じゃない」
目次
第1章月の女神の前で
私がアルファの敵対部族に誘拐されたとき、
当のアルファは彼の『運命の番』とやらと日の出を眺めていた。
電話を受けた彼の声は、ひどく冷めきっていた。「好きにしろ。少しは懲りるだろう。二度と俺に付きまとうなと、よく言い聞かせてやれ」
生死の境で、私に選択の余地はなかった。
敵対部族のアルファに必死にしがみつき、震える声で懇願する。「お願い……殺さないで。あなたに従うから」
ロックがようやく私のことを思い出した頃、敵対部族のアルファは腕の中で眠る私の横顔を見下ろし、嘲笑うかのように言った。「今さら遅い。こいつに、お前と帰る気力など残ってはいない」
……
アルファであるロックと共に十年が経った頃。
彼はついに、月の女神の前で私との誓いを立てることに同意した。
私は胸を躍らせ、彼への贈り物を準備した。
ホテルの個室でようやく見つけた彼は、部下たちと談笑していた。
「本当に明日、ジュリーと誓いの儀式を?」
「まさか。 子供も産めない女に、俺の番になる資格などあるものか」
誰かが笑いながら尋ねる。「彼女に知られて、去られてもいいのですか?」
ロックは侮蔑するように鼻で笑った。「あいつが俺から離れられるなら、の話だがな。たとえ怒って出て行ったところで、三日もすれば泣いて戻ってくる。 賭けてもいい」
部下たちの嘲笑が響き渡る。「確かに、骨のない女ですからな」
その嘲笑を背に、私は凍りついた体でその場を後にした。
翌日の誓いの儀式。精巧なオーダーメイドのスーツに身を包んだ彼は、人々の中心に立ち、
その崇拝を一身に受けていた。
対する私は、普段着のワンピース姿でゆっくりと彼のもとへ歩み寄る。
私に気づいたロックの顔が、みるみるうちに険しくなった。「今日がどれほど重要な日か分かっているのか。俺に恥をかかせる気か?」
私はただ、じっと彼を見つめ返す。「始めましょう」
ロックの視線が、氷の刃のように私を突き刺した。
彼は突如として振り返ると、群衆の中からデビーを壇上へ引き上げた。
その動きでデビーの羽織っていたケープが滑り落ち、まばゆいばかりのウェディングドレスが私の目を焼いた。
「尊き月の女神よ!私、ロックはここに宣言する!我が運命の番はデビーただ一人!どうか我らの証人となりたまえ!」
その場にいた誰もが、私たち三人を固唾をのんで見守っていた。
しかし意外にも、私の顔に絶望の色は浮かばなかった。
そして、誓いの祭壇は何の反応も示さない。
ロックが再び女神に問いかけようとしたのを、私は遮った。
「もう私に用はないでしょう?失礼しても?」
ロックは冷笑を浮かべる。「三日後、泣きながら戻ってくるお前を待っているとしよう」
私は背を向け、その場を去った。大門を抜けた瞬間、堪えていた涙がようやく頬を伝った。
やはり、彼は私のことなど何とも思っていなかったのだ。
昨夜の言葉は、ただの冗談だと思っていた。まさか本当に、衆人環視の中でデビーを選ぶなんて!
私の十年は、一体何だったというの?
彼にとって、私は飽きた玩具に過ぎなかったのか!
二歩ほど歩いたところで、行く手を阻まれた。
デビーが、片手を腰に当てて私の前に立ちはだかる。
「ジュリー、ロックを恨まないで。あなたが役立たずなのがいけないのよ」
「あの方には後継者が必要なの。そしてあなたでは、その役目を果たせない」
得意満面の彼女の顔を見ていると、抑えきれない怒りがこみ上げた。私は彼女を突き飛ばす。「どいて」
次の瞬間、私はロックによって地面に激しく突き倒されていた。
「よくも彼女に手を上げたな。死にたいのか!?」
彼は部下に命じて私を捕らえさせ、罰を与えた。
その夜、私は満身創痍のまま部族から追放された。
月明かりのない漆黒の闇の中、傷だらけの体を引きずって、ただひたすらに歩き続ける。
分かれ道にたどり着いたところで、私の意識は途切れた。
次に意識を取り戻したとき、私は一本の木に縛り付けられていた。すぐ下は、底知れぬ深い崖だ。
「目が覚めたか」
磁力を帯びた声が、すぐそばで響いた。
横を向くと、そこにロンの顔があった――彼もまたアルファであり、ロックと敵対する部族の長だ。
私が目覚めたのを確認すると、ロンはロックに電話をかけた。
「ロック、お前の女は俺が預かった。要求したものは準備できたか?」
一瞬の間を置いて、ロックの笑い声が聞こえてきた。
「好きにしろ。少しは懲りるだろう。二度と俺に付きまとうなと、よく言い聞かせてやれ」
「それから、あいつに伝えろ。次からはもっとマシな気を引く方法を考えろ、と。そんな手はもう古い」
電話が切られ、私の最後の希望も、無慈悲に断ち切られた。
おすすめ
/0/19220/coverbig.jpg?v=e8f8523ce94360559d1d4fc3440d2b7b)
冷遇令嬢、実は天才。婚約破棄した彼らにざまぁ!
田中 翔太桜井陽葵は家族から愛されない「無能で醜い女」とされていた。一方、継母の娘である山口莉子は才色兼備で、間もなく名門一族の後継者・高木峻一と結婚することになり、栄華を極めていた。 人々は皆、強い者に媚びへつらい、弱い者を踏みつけた。山口莉子は特に傲慢で、「桜井陽葵、あなたは永遠に犬のように私の足元に踏みつけられるのよ!」と高らかに言い放った。 しかし、結婚式当日。人々が目にしたのは、豪華なウェディングドレスを纏い、高木家に嫁いだ桜井陽葵の姿だった。逆に山口莉子は笑いものにされる。 街中が唖然とした。なぜ!? 誰もが信じなかった。栄光の申し子・高木峻一が、無能で醜いと蔑まれた女を愛するはずがない。人々は桜井陽葵がすぐに追い出されるのを待ち続けた。 だが待てども待てども、その日が来ることはなかった。現れたのは、眩い光を放つ桜井陽葵の真の姿だった。 医薬界の女王、金融界の大物、鑑定の天才、AI界の教父――次々と明かされる正体の数々が、嘲笑していた者たちの目を眩ませた。 汐風市は騒然となった! 山口家は深く後悔し、幼なじみは態度を翻して彼女に媚びようとする。しかし桜井陽葵が返事をする前に――。 トップ財閥の後継者・高木峻一が発表したのは、桜井陽葵の美しい素顔を捉えた一枚の写真。瞬く間に彼女はSNSのトレンドを席巻したのだった!
/0/17000/coverbig.jpg?v=530e23df1b39e0fa6b12c6fcfa938092)
もう一度、私を殺そうとしたあなたへ
霧島 諒「まだ生きてます。もう一度、轢きますか?」 夫とその愛人に街頭で殺されかけた有栖川朱音。 婚姻生活は虚構、罪まで押しつけられ、最後は“事故死”に仕立て上げられる。 だが、彼女は生きていた。 そして、離婚と同時に、今度はこの街で最も冷酷で美しい男と電撃再婚! 目的は一つ——全てを奪った者たちを、彼と共に叩き潰すこと。 なのにその男が囁く。「偽装のつもりだったけど、本気でもいい?」 地獄から這い上がった彼女の、極上リベンジラブストーリー!
/0/17058/coverbig.jpg?v=4ee2c2e8259a00e8d1ac9e2201018eaa)
この恋が、私の人生を壊した
水無月 ほのか容姿も才能もあり、人生の勝者だと思っていた——氷川詩織は、そう信じていた。 けれど気がつけば、彼女の手札はすべて崩れ去っていた。 中絶、容姿の損壊、仕事の失墜、名誉の破壊——何もかもが壊れていった。 なぜ、こんなことになったのか。 きっと、あの男——一条慎との恋が始まりだった。 愛は人を救うはずだったのに、彼女にとっては地獄の扉だった。 ——これは、一人の女が「愛」を代償に、何を失ったのかを描く痛切な記録。
/0/17003/coverbig.jpg?v=dab14eebb288f4bc42243db406bc2bb1)
元夫よ、見てる?私は今、世界一の男と結婚します
夜月 シオン(よづき しおん)三年耐えた冷たい結婚生活、裏切り、そして離婚。 すべてを終わらせた一ノ瀬光は、過去も愛も捨てて、ただ己の道を突き進む。 トップデザイナー、神業の医師、伝説のハッカー、そして…高嶺の“皇女”。 世間がその名を驚きで語る頃、彼女は新たな人生の扉を開く。 結婚式の日、巨大スクリーンに映し出された彼女と霧島真尋。 その男は世界に向かって高らかに宣言する。 「この女は俺の妻。誰も手出しするな」 元夫が泣いても、もう遅い——彼女は、もう“選ばれる側”ではない。
/0/17126/coverbig.jpg?v=c284a537dace42787d987069265d4245)
別れた翌日、私は“億”の女だった
月城 セナ愛のためにすべてを捨て、三年間“理想の妻”を演じてきた鳳城夢乃。 だが、夫の心にはずっと「初恋の人」がいた。 報われぬ想いに終止符を打ち、ついに彼女は別れを告げる――「本気出すわ、私」。 その翌日、SNSは騒然。正体はなんと、億万資産を持つ若き実業家!? 甘くて痛快な逆転劇。 彼女が本当の自分を取り戻したとき、かつての夫がまさかの土下座会見で…?
/0/17001/coverbig.jpg?v=5d97059fc86a014da0e31371031a239e)
声を持たぬ妻は、愛を捨てた
瀬戸内 晴言葉を持たぬ妻・天野凜に、夫は五年間冷たいままだった。 子さえも奪われ、離婚後すぐに“忘れられない人”との婚約発表。 凜はその日、お腹の子を抱きながらようやく気づく——彼の心に、自分は一度もいなかったと。 すべてを捨て去り、沈黙の彼女は新たな人生へ。 だが、彼女を失ったその日から、男は狂ったように世界中を探し始めた。 再会の日、彼は懇願する。「頼む、行かないでくれ…」 凜は初めて声を発した。「——出ていって」
トップ
 GOOGLE PLAY
GOOGLE PLAY
/0/19225/coverbig.jpg?v=bb915b3ca842acd66a19bc87684ea8d7)