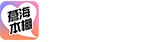3年前、彼は記憶を失った。彼女はその3年間、献身的に彼の世話を続け、誰にも言えない「愛人」としてそばにいた。 ところがある日突然、彼が実は記憶を失っていなかったことを知ってしまう。さらに、彼と本命と呼ばれる女こそが、自分の父を死に追いやった真犯人であることも――。 彼女は胸の痛みに耐えながら証拠を集め、2人の結婚式当日、彼らをそのまま牢獄へと送り込む。 その時になってようやく、彼は気づく。本当に愛していたのは、最初から彼女だったのだと。 だが――遅すぎた愛情など、雑草よりも無価値。彼女はとっくに、彼を捨て去っていた。
目次
第1章偽りの贖罪
蘇清予の父は、過労運転の末に事故を起こし、顧南恒と、彼の想い人である女性に重傷を負わせた。
父の罪を償うため、蘇清予は記憶を失った顧南恒の世話を三年間続けた。彼の、決して公にできない恋人として。
だが、偶然耳にした顧南恒と友人の会話によって、すべてが偽りであったことを知る。彼は記憶など失ってはいなかったのだ。
それどころか、本当の事故原因を隠蔽するために嘘をつき続けていた。
そして、父の命を奪った真犯人は、彼の想い人、何夕瑶だった。
三年間捧げた深い愛情は、踏みにじられた。蘇清予は胸に突き刺さる痛みと戦いながら、証拠を集め始める。
彼らの結婚式の日、とびきりの「贈り物」を手向けるために。
……
顧南恒が飼っている秋田犬は、よく勝手に別荘を抜け出す癖があった。姿が見えなくなった犬を探すため、蘇清予が首輪のGPSに電話をかけると、顧南恒と一緒にいることがわかった。
蘇清予が呼びかけようとした瞬間、顧南恒の特助である冷然の事務的な声が耳に飛び込んできた。
「顧社長、何夕瑶様が来週帰国されます。結婚式のご準備は、そろそろ始められますか?」
「ああ、式まであと半月だ。すぐに取り掛かってくれ。すべて最高級のもので揃えるんだ。夕瑶は目が肥えているからな」
「かしこまりました。以前の事故で何様は重傷を負われ、三年間も海外で治療されていましたが、順調に回復されたとのこと、何よりでございます」
顧南恒が淡々と答える。
「まったく、夕瑶はわがままだ。あの日、無免許にもかかわらず彼女が運転するなどと言い出さなければ、事故など起こらなかった」
冷然が、どこか楽しげな口調で言った。
「ですが、さすがは社長でございます。咄嗟に運転手を蘇海生にすり替え、ご自身は記憶喪失のふりをして蘇清予を騙し通した。これで何様も無事に帰国されますし、もう演技を続ける必要もございません」
「そうだな。三年間、記憶喪失を装った甲斐があった。ただ、蘇清予には少しばかり申し訳ないことをした。彼女の父親が、夕瑶の罪をすべて被ってくれたのだからな」
蘇清予は衝撃に目を見開き、息を殺した。声にならない嗚咽が漏れそうになるのを必死でこらえる。涙だけが、静かに頬を伝って落ちていった。
顧南恒は、記憶を失ってなどいなかった? それに、あの事故の真相は、一体……?
再び冷然の声が響く。
「蘇海生はもともと顧家の運転手です。未来の奥様の身代わりになれたのですから、彼にとっても名誉なことでしょう」
「それに、この数年間、社長が蘇清予に良くしてこられたのも、彼らへの十分な埋め合わせになっているかと存じます」
顧南恒が冷ややかに笑った。
「その通りだ。私が夕瑶と結婚したとしても、蘇清予を蔑ろにするつもりはないさ。 ――-豆包、帰るぞ」
犬の名前を呼ぶ声が聞こえ、蘇清予は慌てて電話を切った。心が巨石に押し潰されるような痛みとめまいに襲われる。
この三年間、私はずっと偽りの中で生きてきたというのか。
蘇清予の母は、彼女が生まれてからずっと病気がちで、亡くなった時には多額の借金が残された。
父である蘇海生と二人、身を寄せ合って生きてきたが、彼女が十四歳の時、父が顧氏グループの御曹司である顧南恒の専属運転手となり、生活はようやく好転した。
しかし三年前、あの事故が起きた。父と相手の車の運転手は即死。後部座席に乗っていた顧南恒と何夕瑶も重傷を負った。
何夕瑶は家族によって海外の病院へ移送され、一命をとりとめた顧南恒は、記憶を失った。
警察は、蘇海生に全責任があると判断し、莫大な賠償金の支払いを命じた。
ようやく上向いてきたばかりの暮らしで、蘇清予にそんな大金を支払えるはずもなかった。そんな彼女に、顧家は賠償金の肩代わりを申し出た。その条件が、記憶を失った顧南恒の世話をすることだった。
蘇清予はもともと顧南恒に想いを寄せていた。その上、自分の父が彼から記憶を奪ってしまったという罪悪感から、一生彼のそばで尽くそうと誓ったのだ。
幸いにも、記憶を失った顧南恒は蘇清予を恨むことなく、常に優しく接してくれた。
そしてある晩、酒に酔った彼に求められ、抗えないまま、蘇清予は彼の秘密の恋人となった。
顧南恒と何夕瑶が婚約関係にあることは知っていた。顧家の恩情に感謝していたし、彼が高嶺の花であることもわきまえていた。ただそばにいられるだけで、満たされていたのだ。
だが、それが救いなどではなく、巧妙に仕組まれた罠だったとは。父の死さえも、顧南恒が何夕瑶を守るための道具に過ぎなかった。
滑稽だ。この三年間、父が彼らに与えた傷を償うことばかり考えてきた。だが、本当に哀れなのは、私たち親子の方だったのだ。
玄関のドアが開く音で、顧南恒が帰宅したとわかった。蘇清予は乱暴に涙を拭い、平静を装う。
「清予、どうして電話に出なかったんだ?」
靴を脱いだ顧南恒は、愛おしそうに彼女を腕の中に閉じ込め、有無を言わさず唇を重ねてきた。
この三年間、彼からの求めを拒んだことは一度もなかった。しかし今日、彼女は本能的に彼を突き放していた。
顧南恒が眉をひそめる。
「どうした? 何か嫌なことでもあったのか? 目が赤い……泣いていたのか?」
彼は心底心配そうに、優しい手つきで蘇清予の頬を撫でた。
蘇清予は目の前の男を見つめた。十四歳から十年もの間、焦がれ続けた人。だが今日、彼に抱いていたすべての幻想は、粉々に砕け散った。
「南恒……もし記憶が戻っても、今と同じように私を愛してくれる?」
顧南恒は一瞬虚を突かれた顔をしたが、すぐに穏やかな笑みを浮かべた。
「馬鹿だな、君。もちろん愛し続けるさ。生涯、君だけを愛すると誓う」
彼はそう言って、彼女の柔らかな唇を再び塞いだ。かつては安らぎを感じたはずの彼の香りが、今はひどく異質なものに感じられる。この唇は、彼女だけを愛すると囁きながら、平気で三年も嘘をつき続けてきたのだ。
一度触れると、顧南恒の理性の箍は外れた。蘇清予の身体は、いつも彼を虜にする。男は荒い息を吐きながら、焦れたように彼女をソファに押し倒した。
もし彼にもう少しの冷静さがあったなら、彼女の頬を伝う絶望の涙に気づいたはずだった。
「君へのプレゼントだ。先日、海外のオークションで競り落とした。きっと君に似合うと思って」
行為の後、顧南恒は宝石のネックレスを蘇清予の首に飾り、その白いうなじに執拗にキスを落とした後、深い眠りに落ちていった。
魂が抜かれたように身を起こした蘇清予は、ネックレスを外し、書斎のジュエリーボックスに仕舞った。中には、ブランド名も知らないような装飾品がいくつも眠っている。身につけることは、ほとんどなかった。
以前はわからなかった。なぜ顧南恒は、体を重ねるたびに贈り物をくれるのだろうと。今ならわかる。彼の心の中で、自分は値札のついた商品なのだ。
与えれば与えるほど、私たち親子に対する罪悪感が薄れるとでも思っているのだろうか。
蘇清予は静かに部屋を片付けながら、涙を流し続けた。彼と結婚できるかどうかなど、どうでもいい。だが、父が濡れ衣を着せられたまま死んだことも、彼に騙され続けたことも、決して許すことはできない。
もう、この偽りの愛に溺れているわけにはいかない。ここを出て、父の無念を晴らすのだ。
深夜、蘇清予は地下駐車場にいた。三年前の事故車両が、修理された後も車庫に保管されていることを思い出したのだ。何か証拠が残っているかもしれない。
車内に残されていたドライブレコーダーを見つけた時、彼女の手は興奮で震えた。
急いで書斎に戻り、映像を確認する。そこには、運転したいと言い出す何夕瑶を、父が穏やかに制する姿が映っていた。
「何様、まだ免許をお持ちでないでしょう。取得されてから……」
父の言葉を遮り、何夕瑶は運転席のドアを開け放つと、乱暴に父を車から引きずり下ろした。
「あんたは顧家の犬でしょ!南恒お兄ちゃんがいいって言ってるんだから、ごちゃごちゃ言わないでよ。とっとと助手席に行きなさい!」
蘇海生は、黙認する顧南恒に一瞥をくれると、おとなしく助手席に移った。だが、それからわずか二分後のことだった。何夕瑶の運転する車は、対向車線にはみ出してしまう。
彼女は恐怖に金切り声を上げた。その瞬間、蘇海生が素早くハンドルを自分の方へ大きく切ったのが見えた。
蘇清予は嗚咽を漏らした。父は、自らの命と引き換えに、何夕瑶に生きる望みを託したのだ。
血まみれの父が、彼女を守るように覆いかぶさっている。
「坊ちゃま……助け……助けてください……」
か細い声で助けを求める父に、後部座席の顧南恒は事故を認識したようだった。しかし彼が最初に取った行動は、父を助けることではなかった。父の体を突き飛ばし、何夕瑶を救い出すことだった。
「南恒お兄ちゃん、私じゃない!事故を起こしたのは運転手の蘇海生よ、そうでしょ? お願い、助けて!刑務所になんて入りたくない!」
泣きながら訴える何夕瑶を、顧南恒は抱きしめて慰め、そして決断を下した。
「夕瑶、君の言う通りだ。運転していたのは蘇海生だ。彼の運転ミスで事故は起きた。すべて彼の責任だ、わかるね? 安心していい。僕が君を守る」
彼は何夕瑶を後部座席に運び、助けを求め続ける蘇海生を運転席に引きずっていった。そして自分は何夕瑶の隣に戻ると、彼女が落ち着くまで慰め続け、それからようやく警察に電話をかけたのだった。
蘇清予の瞳から光が消え、まるで魂を抜き取られたかのようだった。
映像の中、父の服をじわりと染めていく血は、一滴一滴、彼女の心にも流れ込んでくる。
胸を押さえ、大きく息を吸い込む。心臓を抉り取られるような激痛に、喉の奥から押し殺した呻きが漏れた。
(顧南恒、なぜあなたはこんなにも残酷なの?なぜ父を助けてくれなかったの?) 父はいつも、顧家に雇ってもらえたことを感謝していた。心からの敬意を払って、運転手という仕事に誇りを持っていた。
顧南恒が何も言わなくても、善良な父はきっと何夕瑶の罪を被っただろう。
それなのに、彼らは父を信じなかったばかりか、生きる希望さえも奪い去った。
蘇清予は椅子の背にもたれかかった。華奢な肩が、抑えきれずに震えている。
顧南恒、あなたたちの行いには、必ず報いを受けてもらう。
「もしもし、先輩?以前お話しされていた、フランスの翻訳会社からの誘いって、まだ有効ですか?」
電話の向こうで、肖苒苒が喜びに満ちた声を上げた。蘇清予はフランス語学科の秀才だった。何度も誘いをかけていたが、ついに彼女が決心してくれたのだ。
「もちろんよ!急いで出国手続きをして。半月後にでも来てちょうだい」
半月後。 それは、ちょうど顧南恒と何夕瑶の結婚式の日だった。
その日、私は彼らに、とびきりの「贈り物」を届ける。
おすすめ
/0/17126/coverbig.jpg?v=c284a537dace42787d987069265d4245)
別れた翌日、私は“億”の女だった
月城 セナ愛のためにすべてを捨て、三年間“理想の妻”を演じてきた鳳城夢乃。 だが、夫の心にはずっと「初恋の人」がいた。 報われぬ想いに終止符を打ち、ついに彼女は別れを告げる――「本気出すわ、私」。 その翌日、SNSは騒然。正体はなんと、億万資産を持つ若き実業家!? 甘くて痛快な逆転劇。 彼女が本当の自分を取り戻したとき、かつての夫がまさかの土下座会見で…?
/0/19057/coverbig.jpg?v=6adf425183e50931146bf64836d3c51d)
捨てられた妻の華麗なるざまぁ
山本 悠介彼女は、彼の深い愛情を信じてきた。そして、その裏切りもまた目の当たりにした。 彼女は目の前で結婚写真を燃やしたが、彼はただ携帯を抱えて愛人をあやすばかり。 ほんの一瞥すれば気づけたはずなのに、それすらしなかった。 ついに彼女の心は冷え切り、彼の頬を思い切り叩き、愛人との末永い幸せを祝ってやった。 そして振り返ることなく、閉鎖的な研究グループへの加入を申請し、すべての身分情報を抹消した――彼との婚姻関係さえも! ついでに、去り際に一つ“大きな贈り物”を残して。 グループに入った瞬間、彼女は姿を消し、彼の会社は破産の危機に追い込まれる。必死で彼女を探す彼の前に届いたのは、ただ一通の“死亡認定書”だった。 彼は崩れ落ちるように叫ぶ。「信じない、認めない!」 …… 再会のとき、彼は衝撃を受ける。そこに立つ彼女は、もはや別の名を持ち、隣には彼ですら仰ぎ見るほどの権力者がいた。 彼は縋るように懇願する。「俺が悪かった、戻ってきてくれ!」 しかし彼女は眉を上げ、優雅に微笑みながら隣の大人物の腕を取る。 「残念ね。今の私には、もうあなたなんて届かないわ」
/0/17058/coverbig.jpg?v=4ee2c2e8259a00e8d1ac9e2201018eaa)
この恋が、私の人生を壊した
水無月 ほのか容姿も才能もあり、人生の勝者だと思っていた——氷川詩織は、そう信じていた。 けれど気がつけば、彼女の手札はすべて崩れ去っていた。 中絶、容姿の損壊、仕事の失墜、名誉の破壊——何もかもが壊れていった。 なぜ、こんなことになったのか。 きっと、あの男——一条慎との恋が始まりだった。 愛は人を救うはずだったのに、彼女にとっては地獄の扉だった。 ——これは、一人の女が「愛」を代償に、何を失ったのかを描く痛切な記録。
/0/16915/coverbig.jpg?v=89ed53f6c82d5aef26b777477a92c084)
追い出された果てに、億の愛が始まる
藤宮 あやね20年間尽くした水野家に裏切られ、追い出された恩田寧寧。 「本当の親は貧乏だ」——そう思われていたが、その実態は海城一の名門。 億単位の小遣いに、百着のドレスと宝石、そして溺愛されるお嬢様生活。 彼女を侮っていた“元・家族”たちは、次々と彼女の真の素顔に震撼する—— 世界一の投資家、天才エンジニア、F1級のレーサー!? そんな彼女を捨てた元婚約者が、なぜか突然「やっぱり好きだ」と告白? でももう遅い——“本物の兄”とのお見合いが始まってるのだから。
/0/17655/coverbig.jpg?v=4a18214b7258b8ea5928ffc2966592e3)
契約妻は御曹司の独占愛に溺れる
桜宮 薫子お見合い当日、酔いに任せた“一夜の過ち”—— 相手は、都市一の権力を握る御曹司・沈川慎司。 逃げ出そうとした彼女に突きつけられたのは、まさかの「結婚宣言」!? こうして始まった契約結婚生活。 だけどこの夫、想像以上に甘くて強引。 仕事でも、恋でも、彼の独占欲は止まらない! 「噂ではゲイって聞いてたのに!」 「そんなの、信じちゃだめだよ——」 愛されすぎて困っちゃう、スパダリ系旦那との甘くて過激な新婚ライフ♡
トップ
 GOOGLE PLAY
GOOGLE PLAY
/0/19250/coverbig.jpg?v=5163e87b9f0651e30eb8436087605725)

/0/1217/coverbig.jpg?v=def0503074338784a1a0a4beb2a81d34)