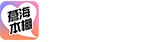夫はシャワーを浴びていた。水の音が、いつもの朝のリズムを刻んでいる。完璧だと思っていた結婚生活、五年目の小さな習慣。私は彼のデスクにコーヒーを置いた。 その時、夫のノートパソコンにメールの通知がポップアップした。「桐谷怜央くんの洗礼式にご招待」。私たちの苗字。送り主は、佐藤美月。SNSで見かけるインフルエンサーだ。 氷のように冷たい絶望が、私の心を支配した。それは彼の息子の招待状。私の知らない、息子の。 私は教会へ向かった。物陰に隠れて中を覗くと、彼が赤ちゃんを抱いていた。彼の黒髪と瞳を受け継いだ、小さな男の子。母親である佐藤美月が、幸せそうな家庭の絵のように、彼の肩に寄りかかっていた。 彼らは家族に見えた。完璧で、幸せな家族。私の世界は、ガラガラと音を立てて崩れ落ちた。 私との子供は、仕事が大変だからと断った彼を思い出す。彼の出張、深夜までの仕事――その時間は、すべて彼女たちと過ごしていたのだろうか? なんて簡単な嘘。どうして私は、こんなにも盲目だったのだろう? 私は、彼のために延期していたチューリッヒ建築学特別研究員制度の事務局に電話をかけた。「研究員制度、お受けしたいと思います」私の声は、不気味なほど穏やかだった。「すぐに出発できます」
目次
第1章
夫はシャワーを浴びていた。水の音が、いつもの朝のリズムを刻んでいる。完璧だと思っていた結婚生活、五年目の小さな習慣。私は彼のデスクにコーヒーを置いた。
その時、夫のノートパソコンにメールの通知がポップアップした。「桐谷怜央くんの洗礼式にご招待」。私たちの苗字。送り主は、佐藤美月。SNSで見かけるインフルエンサーだ。
氷のように冷たい絶望が、私の心を支配した。それは彼の息子の招待状。私の知らない、息子の。
私は教会へ向かった。物陰に隠れて中を覗くと、彼が赤ちゃんを抱いていた。彼の黒髪と瞳を受け継いだ、小さな男の子。母親である佐藤美月が、幸せそうな家庭の絵のように、彼の肩に寄りかかっていた。
彼らは家族に見えた。完璧で、幸せな家族。私の世界は、ガラガラと音を立てて崩れ落ちた。
私との子供は、仕事が大変だからと断った彼を思い出す。彼の出張、深夜までの仕事――その時間は、すべて彼女たちと過ごしていたのだろうか?
なんて簡単な嘘。どうして私は、こんなにも盲目だったのだろう?
私は、彼のために延期していたチューリッヒ建築学特別研究員制度の事務局に電話をかけた。「研究員制度、お受けしたいと思います」私の声は、不気味なほど穏やかだった。「すぐに出発できます」
第1章
夫の蓮はシャワーを浴びていた。ガラスに叩きつけられる水の音が、いつもの朝のリズムを刻んでいる。私は彼のデスクにコーヒーを置いた。完璧だと思っていた結婚生活、五年目の小さな習慣。
その時、蓮のノートパソコンの画面に、カレンダーからのミニマルなポップアップ通知が滑り込んできた。
目を逸らす前に、その文字が飛び込んできた。
「桐谷怜央くんの洗礼式にご招待」
その名前に、私は凍りついた。桐谷怜央。私たちの苗字。
私がそれを理解する前に、通知は消えた。一瞬のまたたき。そして、消えた。まるで、最初からそこになかったかのように。
でも、もう遅い。その映像は、私の脳裏に焼き付いていた。送り主は、佐藤美月。どこかで聞いたことのある名前。時々フィードに流れてくる、完璧に作り上げられた生活を見せびらかすSNSインフルエンサー。フォロワーが何十万もいる、美しい女性。
冷たく鋭い不安が、胃の腑に突き刺さった。これはただのランダムなメールじゃない。彼の息子の招待状。私の知らない、息子の。
住所は都心の教会。時間は、今日の午後。
ノートパソコンを閉じて、何も見なかったことにしたい。蓮と築き上げてきた完璧な幻想に戻りたい。私を愛してくれた、聡明でカリスマ的なIT企業のCEO、蓮との生活に。
でも、もう一人の私が、冷たく、しつこく囁く。行かなければ。確かめなければ、と。
私はコーヒーをデスクに残し、私たちの家を出た。私が私たちの愛の記念碑として設計した、清潔でミニマルな家を。
教会は古い石造りで、ステンドグラスから陽光が差し込んでいた。私は後ろの方に立ち、物陰に隠れた。心臓が、重く、痛みを伴って肋骨を叩く。
そして、彼を見た。
蓮。私の蓮。彼はいつものシャープなビジネススーツではなく、柔らかいカジュアルな服を着て、前の方に立っていた。リラックスして、幸せそうに見えた。白いレースに包まれた美しい赤ちゃんを抱いている。
蓮の黒髪と、表情豊かな瞳を持つ、小さな男の子。
その子、怜央くんが、ぷっと泡を吹いて笑い、小さな手を伸ばして蓮の顔に触れた。
「あなたみたいな人になってほしいな、パパ」女の声が、柔らかく、所有権を主張するように言った。
佐藤美月が姿を現し、蓮の腰に腕を回した。彼女は蓮の肩に頭を寄せ、幸せな家庭の絵そのものだった。彼女の笑顔は輝き、その目は私が夫と呼ぶ男に釘付けになっていた。
彼らは家族に見えた。完璧で、幸せな家族。
私の頭は真っ白になった。あまりに深い無感覚の波が押し寄せ、まるで自分の体から魂が抜け出して浮いているようだった。蓮が美月の額にキスをし、そして赤ん坊に注意を戻し、何かを囁いて彼女を笑わせるのを、私はただ見ていた。
現実だった。すべてが。女も、赤ん坊も。彼の秘密の生活も。
信者席には見覚えのある顔がいくつかあった。蓮の仕事仲間で、私たちの家のディナーパーティーに来たことのある人たちだ。彼らは幸せそうなカップルに微笑みかけ、物陰で世界が崩壊していく妻の存在には気づいていない。
息ができなかった。そこへ歩み寄り、叫び、彼らの完璧な瞬間を粉々にする勇気はなかった。闘志は消え失せ、代わりに深く、空虚な絶望が私を支配した。
私は踵を返し、重い教会の扉から滑り出て、街の喧騒の中へと戻った。音はくぐもって、遠くに聞こえる。世界は冷たく、私はそれ以上に冷え切っていた。
数ヶ月前の記念日の会話を思い出した。
「蓮」私は優しく言った。「私、準備ができたと思うの。赤ちゃん、作らない?」
彼は黙り込んだ。目を逸らし、髪を手でかき上げた。いつも彼が考え事をするときの癖だと思っていた。
「まだだよ、詩織」彼はついに言った。「会社が正念場なんだ。もう一年だけ待ってくれ。子供には、すべてを与えられる状態でいたいんだ」
私は彼を信じていた。大学時代、私を執拗に追いかけた男を信じていた。私の野心の奥にある、ただの女としての私を見てくれた唯一の人。
当時、私たちは建築学科のトップを争うライバルだった。彼は聡明で、野心的で、私以外の誰にでも冷たかった。
私がスタジオで徹夜していると、温かいスープを持ってきてくれたのを覚えている。設計図に向かってかがむ私の背中を、彼の手が優しくさすってくれた。
肺炎で倒れ、立つこともままならなかった時のことも。彼は三日間、病院のベッドのそばに付きっきりで、眠りもせず、ただ私を見守ってくれた。
彼はその病室でプロポーズした。見たこともないほど脆い声で。
「詩織を失うわけにはいかない」彼は私の額に自分の額を押し付け、囁いた。「君のいない人生なんて、考えられない」
後で知ったことだが、彼の母親も同じような病院で亡くなっていた。彼の恐怖は本物だと感じたし、彼の愛は絶対だと思っていた。
私たちは卒業後すぐに結婚した。彼のITスタートアップは爆発的に成功し、彼は誰もが憧れる男になった。私も自分のキャリアを築いたが、常に彼を優先した。彼のために、私たちのために、私自身の五年計画を変更した。
そして、その間ずっと、彼には別の家族がいたのだ。
私だけに向けられていると信じていたあの愛も、献身も、嘘だった。ただの演技だった。
ポケットの中でスマホが震えた。彼からだった。画面に表示された彼の名前を、震える手で見つめる。やっとのことで応答した。
「もしもし、どこにいるんだ?」彼の声は温かく、いつも私に使う愛情のこもった口調だった。
背景から、赤ん坊の泣き声が微かに聞こえ、そして美月が子供をあやす声がした。
私は教会の向かいの通りに立ち、開いた扉から彼を見ていた。彼はスマホを耳に当て、私に話しかけながら微笑んでいる。
「ちょっと散歩してるだけ」なんとかそう言うと、自分の声が異質で、脆く聞こえた。
「急な会議で捕まっちゃって」彼は滑らかに言った。「もうすぐ帰るから。会いたいよ」
なんて簡単な嘘。彼の口からは、呼吸をするように嘘が吐き出される。ついに一筋の涙がこぼれ落ち、冷たい肌を熱く伝った。数々の出張、オフィスでの深夜残業。そのうちのどれだけが、ここで、彼女たちと過ごされていたのだろう?
どうして私は、こんなにも盲目だったのだろう?
喉の奥の塊を飲み込み、声を無理やり安定させた。「蓮、会って話したいことがあるの」
彼はためらった。彼が体重を移動させ、笑顔が一瞬だけ揺らぐのが見えた。「まだ会議中なんだ、ハニー。家に帰るまで待てないか?」
「待てない」
その時、小さな男の子、怜央くんがよちよちと歩いてきて、蓮の足に抱きついた。
「パパ!」子供が甲高い声を上げた。
蓮の目はパニックで見開かれた。彼は慌ててかがみ込み、私には落ち着いた低い声を保ちながら、男の子を静かにさせようとした。「ああ…同僚の子供だよ」
電話が切れた。彼が切ったのだ。
彼が男の子を腕に抱き上げ、頬にキスをし、何かを囁いて子供を笑わせるのを見ていた。彼はとても自然で、くつろいで見えた。なんて良い父親だろう。
私の心はえぐり取られたように、空っぽで、痛みを伴う空洞だけが残った。私の人生の数年間、私の愛が、まるで冗談のように感じられた。
私は再びスマホを取り出した。指が勝手に動いていた。親友の由奈には電話しなかった。弁護士にも電話しなかった。
私が電話したのは、チューリッヒ建築学特別研究員制度のディレクターだった。私が合格したにもかかわらず、蓮のために延期した、名誉ある六ヶ月間のプログラム。完全な、途切れることのない集中を要求されるプログラム。完全な隔離。
「研究員制度、お受けしたいと思います」私の声は、不気味なほど穏やかだった。「すぐに出発できます」
Gavinのその他の作品
もっと見る/0/19686/coverbig.jpg?v=f49e67a627832a869b973aae0e0fb2e6)
愛が灰燼と化すとき
短編私の世界のすべては、桐谷蓮を中心に回っていた。兄の親友で、人を惹きつけてやまないロックスターの彼に。 十六歳の頃から、私は蓮に憧れていた。そして十八歳の時、彼の何気ない一言に、藁にもすがる思いでしがみついた。「お前が二十二になったら、俺も身を固める気になるかもな」 その冗談みたいな言葉が、私の人生の道しるべになった。すべての選択は、その言葉に導かれた。二十二歳の誕生日こそが、私たちの運命の日だと信じて、すべてを計画した。 でも、下北沢のバーで迎えた、その運命の日。プレゼントを握りしめた私の夢は、木っ端微塵に砕け散った。 蓮の冷たい声が聞こえてきた。「マジかよ、沙英が本当に来るとはな。俺が昔言ったくだらないこと、まだ信じてやがる」 そして、残酷すぎる筋書きが続いた。「怜佳と婚約したってことにする。なんなら、妊娠してるって匂わせてもいい。それでアイツも完全に諦めるだろ」 プレゼントが、私の未来が、感覚を失った指から滑り落ちた。 裏切りに打ちのめされ、私は冷たい東京の雨の中へ逃げ出した。 後日、蓮は怜佳を「婚約者」として紹介した。バンド仲間が私の「健気な片想い」を笑いものにする中、彼は何もしなかった。 アートオブジェが落下した時、彼は怜佳を救い、私を見捨てた。私は重傷を負った。 病院に現れた彼は「後始末」のためだった。そして信じられないことに、私を噴水に突き飛ばし、血を流す私を置き去りにした。「嫉妬に狂ったヤバい女」と罵って。 どうして。かつて私を救ってくれた、愛したはずの人が、こんなにも残酷になれるの? なぜ私の献身は、嘘と暴力で無慈悲に消し去られるべき迷惑なものになったの? 私はただの邪魔者で、私の忠誠心は憎悪で返されるべきものだったの? 彼の被害者になんて、ならない。 傷つき、裏切られた私は、揺るぎない誓いを立てた。もう、終わり。 彼と、彼につながるすべての人間の番号をブロックし、縁を切った。 これは逃避じゃない。私の、再生。 フィレンツェが待っている。壊れた約束に縛られない、私のための新しい人生が。
/0/19683/coverbig.jpg?v=ddd0a6c19347cb9426feaf973a026235)
片思いの代償
短編高遠湊を諦めてから、十八日。 有栖川詩織は、腰まであった長い髪をばっさりと切った。 そして父に電話をかけ、福岡へ行き、慶應大学に通う決意を告げた。 電話の向こうで驚いた父は、どうして急に心変わりしたんだと尋ねてきた。 お前はいつも、湊くんと一緒にいたいと言って、横浜を離れようとしなかったじゃないか、と。 詩織は無理に笑ってみせた。 胸が張り裂けるような、残酷な真実を打ち明ける。 湊が、結婚するのだと。 だからもう、血の繋がらない妹である自分が、彼にまとわりついていてはいけないのだと。 その夜、詩織は湊に大学の合格通知を見せようとした。 けれど、彼の婚約者である白石英梨からの弾むような電話がそれを遮った。 英梨に愛を囁く湊の優しい声が、詩織の心を締め付けた。 かつて、その優しさは自分だけのものだったのに。 彼が自分を守ってくれたこと、日記やラブレターに想いのすべてをぶつけたこと、そして、それを読んだ彼が激昂し、「俺はお前の兄だぞ!」と叫びながら手紙をビリビリに破り捨てた日のことを、詩織は思い出していた。 彼は嵐のように家を飛び出し、詩織は一人、粉々になった手紙の破片を painstakingにテープで貼り合わせた。 それでも、彼女の恋心は消えなかった。 彼が英梨を家に連れてきて、「義姉さん、と呼べ」と命じたときでさえ。 でも、今はもうわかった。 この燃え盛る想いは、自分で消さなければならない。 自分の心から、高遠湊という存在を、抉り出さなければならないのだ。
/0/19684/coverbig.jpg?v=ba1bf062f0fb997e704691daf149a575)
絶望の淵から、億万長者の花嫁へ
短編父は七人の優秀な孤児を、私の夫候補として育て上げた。 何年もの間、私の目にはその中の一人、冷たくて孤高の黒崎蓮しか映っていなかった。 彼のその態度は、私が打ち破るべき壁なのだと、そう信じていた。 その信念が砕け散ったのは、昨夜のこと。 庭で、彼が義理の妹であるエヴァ――父が彼の頼みで引き取った、私が実の妹のように可愛がってきた、あの儚げな少女――にキスしているのを見つけてしまったのだ。 だが、本当の恐怖は、書斎で他の六人のスカラーたちの会話を盗み聞きしてしまった時に訪れた。 彼らは私を巡って争ってなどいなかった。 彼らは結託し、「事故」を演出し、私の「愚かで盲目な」献身を嘲笑い、私を蓮から遠ざけようとしていたのだ。 彼らの忠誠心は、彼らの未来をその手に握る私、神宮寺家の令嬢に向けられたものではなかった。 エヴァに向けられていたのだ。 私は勝ち取られるべき女ではなかった。 ただ管理されるべき、愚かなお荷物だった。 共に育ち、我が家に全てを負っているはずの七人の男たちは、カルト教団であり、彼女はその女王だったのだ。 今朝、私は彼らの世界を焼き尽くす決断を下すため、父の書斎へと向かった。 父は微笑み、ようやく蓮を射止めたのかと尋ねてきた。 「いいえ、お父様」 私は毅然とした声で言った。 「私が結婚するのは、狩野湊さんです」
/0/19678/coverbig.jpg?v=0019cf9b553fce2e5521a6f9e2b9da40)
彼の隠し子、彼女の公衆の恥辱
短編私の名前は道明寺愛奈。研修医として働きながら、幼い頃に生き別れた裕福な家族と、ようやく再会を果たした。私には愛情深い両親と、ハンサムで成功した婚約者がいる。安全で、愛されている。それは完璧で、そして脆い嘘だった。 その嘘が粉々に砕け散ったのは、ある火曜日のこと。婚約者の海斗が役員会議だと言っていたのに、実際は広大な屋敷で、ある女と一緒にいるのを見つけてしまったから。朝倉希良。五年前、私に罪を着せようとして精神を病んだと聞かされていた女。 落ちぶれた姿ではなかった。彼女は輝くような美しさで、海斗の腕の中で笑うレオという小さな男の子を抱いていた。 漏れ聞こえてきた会話。レオは二人の息子。私はただの「繋ぎ」。海斗が私の実家のコネを必要としなくなるまでの、都合のいい存在。そして、私の両親…道明寺家の人間も、すべてを知っていた。希良の贅沢な暮らしと、この秘密の家庭を、ずっと援助していたのだ。 私の現実のすべてが――愛情深い両親も、献身的な婚約者も、ようやく手に入れたはずの安心も――すべてが、巧妙に仕組まれた舞台装置だった。そして私は、主役を演じる愚かな道化に過ぎなかった。海斗が、本物の家族の隣に立ちながら私に送ってきた「会議、今終わった。疲れたよ。会いたいな。家で待ってて」という、あまりにも無神経な嘘のメッセージが、最後のとどめになった。 奴らは私を哀れだと思っていた。馬鹿だと思っていた。 その考えが、どれほど間違っていたか。もうすぐ、思い知ることになる。
おすすめ
/0/19545/coverbig.jpg?v=edd8f2129eba477569eaa05e01023bd3)
出所した悪女は、無双する
時雨 健太小林美咲は佐久間家の令嬢として17年間生きてきたが、ある日突然、自分が偽物の令嬢であることを知らされる。 本物の令嬢は自らの地位を固めるため、彼女に濡れ衣を着せ陥れた。婚約者を含む佐久間家の人間は皆、本物の令嬢の味方をし、彼女を自らの手で刑務所へと送った。 本物の令嬢の身代わりとして4年間服役し出所した後、小林美咲は踵を返し、東條グループのあの放蕩無頼で道楽者の隠し子に嫁いだ。 誰もが小林美咲の人生はもう終わりだと思っていた。しかしある日、佐久間家の人間は突然気づくことになる。世界のハイエンドジュエリーブランドの創設者が小林美咲であり、トップクラスのハッカーも、予約困難なカリスマ料理人も、世界を席巻したゲームデザイナーも小林美咲であり、そしてかつて陰ながら佐久間家を支えていたのも、小林美咲だったということに。 佐久間家の当主と夫人は言う。「美咲、私たちが間違っていた。どうか戻ってきて佐久間家を救ってくれないか!」 かつて傲慢だった佐久間家の若様は人々の前で懇願する。「美咲、全部兄さんが悪かった。兄さんを許してくれないか?」 あの気品あふれる長野家の一人息子はひざまずきプロポーズする。「美咲、君がいないと、僕は生きていけないんだ」 東條幸雄は妻がとんでもない大物だと知った後、なすがままに受け入れるしかなくなり…… 他人から「堂々とヒモ生活を送っている」と罵られても、彼は笑って小林美咲の肩を抱き、こう言うのだった。「美咲、家に帰ろう」 そして後になって小林美咲は知ることになる。自分のこのヒモ旦那が、実は伝説の、あの神秘に包まれた財界のレジェンドだったとは。 そして、彼が自分に対してとっくの昔から良からぬことを企んでいたことにも……
/0/17333/coverbig.jpg?v=ab8c582413ed19a11aae8a8cc2a391b3)
契約妻を辞めたら、元夫が泣きついてきた
藤宮 あやね冷徹な契約結婚のはずが、気づけば本気になっていた―― 藤沢諒との結婚生活で、神崎桜奈はただひたすらに尽くしてきた。 だが火災の夜、彼が守ったのは「初恋の彼女」。 心が砕けた彼女は静かに家を去り、すべてを捨てて離婚届に判を押す。 ……数ヶ月後、彼女は別人のように華やかに輝いていた。 恋敵たちが列をなす中、彼は懇願する。「君がいないとダメなんだ、やり直そう」 その言葉に、彼女は微笑む――「再婚希望?じゃあ四千万円から並んでね」
/0/17004/coverbig.jpg?v=9d34d2b07e68e891ef48c799177edf59)
フラれた翌日に結婚したら、億万長者の妻になってました
緋色 カケル失恋の翌日、勢いで見知らぬ男と結婚した七瀬結衣。 どうせすぐ破産すると言う彼を支えるつもりだったが——なぜか彼は異常に頼れる。 ピンチのたびに現れては完璧に解決。どう見ても“運だけ”じゃない! 実はその正体、世界一の大富豪・朝倉誠司。 「これが君の“運の良さ”だよ」 ——波乱のスタートだった“契約結婚”は、いつしか本物の愛へと変わっていく。
/0/16912/coverbig.jpg?v=6094500432b1f7394a537c696ae01d2f)
離婚後、腹黒エリートの愛が止まらない
月城 セナ10年尽くした恋の終着点は、冷たい離婚届と嘲笑だった。 「跪いて頼めば、戻ってやってもいい」——冷泉木遠のその言葉に、赤楚悠はきっぱりと背を向ける。 三ヶ月後、世間が震えた。 彼女は世界的ブランド“LX”の正体不明のデザイナー、億を動かす実業家、そして…伝説の男・周藤社長に溺愛される女。 跪いて懇願する冷家に、彼女はただ一言。 「今の私は、あなたたちには高嶺の花すぎるの」 ——逆転と誇りに満ちた、爽快リベンジ・シンデレラストーリー!
/0/18034/coverbig.jpg?v=63ff8b3a25ffd30a75f58fd39800ca48)
愛を諦めたあの日、彼はまだ私を手放していなかった
ぷに林めい結婚二年目、赤子を宿した白川明澄に届いたのは――離婚届。そして交通事故、流れる血の中で彼に助けを乞うも、腕に抱かれていたのは初恋の人だった。命と心を喪い、彼女は静かに目を閉じた。数年後、「白川明澄」という名は藤原誠司にとって禁句となった。彼女が他の男と結婚式を挙げるその日、彼は叫ぶ。「俺の子を連れて、誰と結ばれる気だ?」——愛は終わったはずだった。だが、終わらせたのは誰だったのか。
/0/19031/coverbig.jpg?v=d4739ef41abb58baa114c66a1e004b54)
捨てられ花嫁、隣の席で運命が動き出す
高橋 結衣婚礼の席、新郎は星川理緒を置き去りにし、本命を追って去ってしまった。 その隣の会場では、花嫁が新郎が車椅子に乗っていることを理由に結婚を拒み、姿を見せなかった。 車椅子に座るその新郎を見て、星川理緒は苦笑する。 ──同じ境遇なら、いっそ一緒になってもいいのでは? 周囲からの嘲笑を背に、星川理緒は彼のもとへと歩み寄る。 「あなたは花嫁がいない。私は花婿がいない。だったら、私たちが結婚するっていうのはどうかしら?」 星川理緒は、彼が哀れな人だと思い込み、「この人を絶対に幸せにしてみせる」と心に誓った。 …… 結婚前の一之瀬悠介「彼女が俺と結婚するのは、金が目当てに決まってる。用が済んだら離婚するつもりだ。」 結婚後の一之瀬悠介「妻が毎日離婚したがってる……俺はしたくない。どうすればいいんだ?」
トップ
 GOOGLE PLAY
GOOGLE PLAY
/0/19679/coverbig.jpg?v=7c95aac02237827ae353d9478289c872)