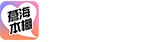セリナは、マフィアファミリーの私生児であるカイアス・カポネ氏に10年間仕えていた。 しかし彼が実権を握った日、一族の者たちは別人を「教母」と呼んだ。 カイアス・カポネ氏の血に濡れ銃を握る手は、一人の清純な美人を抱きしめていた。 「セリナ、俺を責めないでくれ。君は高等教育を受けていないし、奔放すぎる。マフィアの『教母』にはふさわしくない」 「シロデは君とは違う。彼女は高貴な生まれで、楽団の第二ヴァイオリン首席でもある。 君は名分がなくとも私についてこられるが、彼女はそうはいかない」 セリナは騒がず、振り返って立ち去った。 カイアス・カポネ氏は知らなかった。彼女が最も強大なマフィアファミリーの王女であり、シロデ様が所属する楽団の第一首席でもあることを。 メネスヴァ家はセリナが愚行に走っていることを知っており、とうの昔に彼女のために男を用意していた。 カイアス・カポネ氏が必死に取り入ろうとしている武器商人が、彼女の婚約者になろうと躍起になっている。
目次
第1章
カイエスが教父に就任する前夜、彼は薬を二粒飲み、セリーナを連れて激しく情熱を燃やした夜を過ごした。
暗い森からマイバッハの後部座席、浴室、そして最後には彼女の腰を掴んで大きなベッドに投げ込む。
セリーナは擦り傷で痛む体を横たえながら、破れたセクシーなナイトウェアを見て、かすれた声で尋ねた。
「カイエス、明日の太陽が見えないの?」欲望に満ちた狂気の極みだった。
カイエスは一本のシガーに火をつけた。
その煙が彼の表情を曖昧にする。
「セリーナ、もし俺が君と別れたいと言ったら、君は俺のために命を懸けたりしないだろう?」彼の気軽な口調は冗談のように聞こえたが、セリーナは冷ややかに感じた。
彼女はカイエスと10年を過ごし、彼をよく知っていた。
しかし今日、彼の試すような冗談にどれほどの真意が隠されているのか、彼女は見極められなかった。
セリーナは身を起こし、目を細めて彼を見た。
絹の布団が滑り落ち、彼女の裸の肩と背中が露わになった。
ふたりの視線が交わるが、誰も口を開けなかった。
セリーナは動いた。
彼女は湧き上がる感情を抑え、彼の手からシガーを奪い取った。
深く吸い込み、煙を彼の顔に吐き出した。
「カイエス、もう10年経ったわ。
」10年前なら、純粋で頑固なセリーナは命をかけてでも彼の側に留まろうとしただろう。
しかし今、彼女は27歳だ。
後半の言葉は言わなかったが、カイエスは理解し、暗黙の了解があった。
彼は彼女の口角に軽くキスをした。
「じゃあ、これで終わりにしよう、セリーナ。
俺たちもいい歳だから、これ以上騒ぐのは見苦しい。
」セリーナはシガーを挟んだ手を止めた。
暗闇の中で涙が彼女の目から溢れ、メイクを滲ませた。
シガーが燃え尽きて彼女の指先を焼き、痛みを感じた。
彼女はようやく何事もないように振る舞ったが、心の内は嵐のようだった。
「いいわ。 」
セリーナはベッドから降りて、下着を拾い上げて着ようとしたが、カイエスが彼女の腰を抱き寄せてまた抱きしめた。
密集したキスが彼女の肌に赤い痕を残した。
彼は馴れた手つきで彼女のブラを直し、後ろから抱きしめ、以前のように彼女の肩に顎を置いた。
「来月、俺結婚するんだけど、君は来る?」セリーナの胸が締め付けられた。
こんなに早く?彼との別れから次の女性との結婚まで、こんなに早く?彼女は一瞬言葉を失った。
「黙っているなら、来るってことだ。 」
カイエスは寝台の引き出しを開け、招待状を取り出して彼女の胸に押し込んだ。
セリーナの体が震えた。
招待状の冷たい感触か、カイエスの軽薄な行動が彼女を不快にさせたのか。
彼は彼女の顔を軽く叩き、ペットをからかうように。
「今日は遅いから、明日の朝に出発しよう。 もう一晩、俺と一緒にいてくれ。
」その口調は甘く曖昧だが、拒絶は許されなかった。
もちろん、この10年間、セリーナは彼に何も拒んだことはなかった。
彼女は彼に従順であったため、彼はセリーナの本当の性格を忘れてしまった。
冷徹で、決断したら揺るがない性格。
セリーナは彼の手を押しのけ、彼の胸から身を起こした。
「明日の朝に出発するのは遅すぎる。
」彼はすぐに結婚するのだから、彼女が彼と曖昧な関係を続ければ、本当に浮気相手になってしまう。
カイエスは彼女の言葉の意味を理解した。
彼は目を細めた。
「セリーナ、俺たちは合わない。
」彼は彼の婚約者について話し始め、口調がいくらか優しくなった。
「彼女はシローダイという名前で、オーリオン・ウォードハーストの妹だ。 オーリオンはサプライヤーで、俺は彼との関係を求めている。 」
セリーナは眉をひそめた。
オーリオン・ウォードハーストは、裏社会で広く知られている有名な武器商人だ。
行動は秘密裏に行われ、気まぐれで、どのマフィアの家族も彼との協力を得れば、短期間で何倍にも強大になることができる。
カイエスは彼女の異変に気づかず、続けた。
「彼女は君とは違って、純粋すぎて、名のない状態で俺といることはできないんだ。
君は自由を楽しんでいるから、付き合うのは楽しいけれど、結婚には向いていない。 」
セリーナは鼻先がツンとし、涙がまたこぼれそうになった。
愛欲の香りが漂う中で、彼女は肌の赤紫の痕を見て、破れたレースの布を見つめた。
彼女の心には石が詰まっているようで、息が詰まる。
彼の言葉は、彼女がただの遊び相手として楽しむ価値しかないということなのか?彼はどうしてそんなことができるのか?
煙で化粧が濃くなり、レース、黒いストッキング、タイトなスカート。
これらはカイエスの好みで、セリーナは彼に合わせて無理に自分を変えた。
彼のために少しずつ魅惑的でセクシーになり、自分自身も認識できないほど変わったのに、彼は彼女を軽蔑し、彼女を軽薄だと感じた。
セリーナは冷たい表情で、問いただす言葉を口にした。
「あなたは…」しかしカイエスは淡々と彼女を遮り、震えるスマホを振った。
「電話を取るよ。
」向こう側から、シローダイの優しい声が聞こえてきた。
「カイエス、今夜は流星が見えるよ。 私と一緒に見に行かない?」
おすすめ
/0/17332/coverbig.jpg?v=ccb99d3220a8db315143e23210439794)
離婚したら、元夫が知らなかった私が目を覚ました
桜井 あんず「君なんて最初から必要なかった」 夫の冷たい一言で、榛名文祢の四年間の結婚は幕を閉じた。 家族のための政略結婚、心の中にいるのは宝木理紗だけ――そう告げられた彼女は、静かに立ち去る。 だが、去ったのは黒岩奥様であり、帰ってきたのは業界を震撼させる実力派カリスマ。 華やかな舞台で輝きを放つさくらを見て、前夫は戸惑い、嫉妬し、そして……気づく。 「君は最初から、誰よりも眩しかった」 けれどその隣には、すでに新たな男がいて——?
/0/16915/coverbig.jpg?v=89ed53f6c82d5aef26b777477a92c084)
追い出された果てに、億の愛が始まる
藤宮 あやね20年間尽くした水野家に裏切られ、追い出された恩田寧寧。 「本当の親は貧乏だ」——そう思われていたが、その実態は海城一の名門。 億単位の小遣いに、百着のドレスと宝石、そして溺愛されるお嬢様生活。 彼女を侮っていた“元・家族”たちは、次々と彼女の真の素顔に震撼する—— 世界一の投資家、天才エンジニア、F1級のレーサー!? そんな彼女を捨てた元婚約者が、なぜか突然「やっぱり好きだ」と告白? でももう遅い——“本物の兄”とのお見合いが始まってるのだから。
/0/19325/coverbig.jpg?v=5ca1ca27d41583231a2b059d3695f96c)
元妻に跪く冷徹社長
朝霧 知恵三年前、彼女は周囲から嘲笑を浴びながらも、植物状態の彼と結婚するという固い決意を貫いた。 三年後、彼女が不治の病を患い、中絶を余儀なくされたその時、夫は別の女性のために、世間の注目を浴びながら大金を投じていた。 手術室から出てきた時、夫を深く愛していた彼女の心もまた、死んだ。「あなた、離婚しましょう!」 離婚すれば他人同士。彼はきらびやかな女性関係を、自分は残された人生を謳歌する。 そう思っていたのに―― 「俺が悪かった。帰ってきてくれないか?」 冷徹で気高かったはずの元夫が、プライドを捨てて元妻の前にひざまずく。「頼むから、俺のそばに戻ってきてくれ」 彼女は差し出された薔薇を冷たく突き放し、胸を張って言い放った。「もう遅いわ!」
/0/18034/coverbig.jpg?v=63ff8b3a25ffd30a75f58fd39800ca48)
愛を諦めたあの日、彼はまだ私を手放していなかった
ぷに林めい結婚二年目、赤子を宿した白川明澄に届いたのは――離婚届。そして交通事故、流れる血の中で彼に助けを乞うも、腕に抱かれていたのは初恋の人だった。命と心を喪い、彼女は静かに目を閉じた。数年後、「白川明澄」という名は藤原誠司にとって禁句となった。彼女が他の男と結婚式を挙げるその日、彼は叫ぶ。「俺の子を連れて、誰と結ばれる気だ?」——愛は終わったはずだった。だが、終わらせたのは誰だったのか。
/0/17001/coverbig.jpg?v=5d97059fc86a014da0e31371031a239e)
声を持たぬ妻は、愛を捨てた
瀬戸内 晴言葉を持たぬ妻・天野凜に、夫は五年間冷たいままだった。 子さえも奪われ、離婚後すぐに“忘れられない人”との婚約発表。 凜はその日、お腹の子を抱きながらようやく気づく——彼の心に、自分は一度もいなかったと。 すべてを捨て去り、沈黙の彼女は新たな人生へ。 だが、彼女を失ったその日から、男は狂ったように世界中を探し始めた。 再会の日、彼は懇願する。「頼む、行かないでくれ…」 凜は初めて声を発した。「——出ていって」
/0/16871/coverbig.jpg?v=41d448583624096a3538ad44241991a3)
小悪魔な君を、甘やかしたい――病み系社長の愛情攻撃
花園 みお裏切り、中傷、家族の崩壊、そして悲劇の最期。 白川南音の前世は、あまりにも残酷だった。 だが生まれ変わった今、彼女はもう騙されない。 恩?恋?同情?——そんなもの、全て捨てて構わない。 渾身の力で裏切り者を潰し、没落した一族を再興し、彼女は今度こそ人生を取り戻す。 そして再び出会ったのは、前世で唯一手の届かなかった男。 「前回は間に合わなかった。でも今度こそ、君を迎えに来た」 ——復讐と再生、そして予期せぬ愛が交錯する、逆転ヒロイン・ロマンス。
トップ
 GOOGLE PLAY
GOOGLE PLAY
/0/20074/coverbig.jpg?v=84cb10aa678a44dc196adf5286381105)