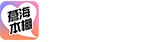「おまえみたいに弱い狼は、ゴミでも食っていろ」 義父は、自分の精子まみれの果皮を無理やり食べさせようとしてきた。 必死に抵抗して逃れようとしたが、両手を折られてしまう。 涙が目に溢れ、胸の内は恐怖と絶望でいっぱいだった。 「やめろ!」 そのとき、聞き慣れた力強い声が響いた。 いつの間にか部屋の入口に立っていた男の顔には、怒りが浮かんでいた。 それは圧倒的なアルファだった。 義父は一瞬たじろぎ、すぐに私を放した。狼狽の色が瞳をよぎる。 私はその隙に逃れ、ふらつきながらも男の背後に身を隠して震えた。 「どうして自分の娘にこんなことをするんだ!」 アルファは義父を睨みつける。 義父は何も答えず、ただ私を鋭く睨みつけると、家を出ていった。 私はそのアルファにしがみついた。 彼は背中を優しく叩きながら慰めてくれる。「もう大丈夫だ。あいつは二度とおまえを傷つけられない。」 その瞬間、初めて心からの温もりを感じた。 やがて私は彼のルナとなり、永遠の幸福を信じていた。 だが、その思いは10周年の記念日に崩れ去った。 彼の初恋の女が群れに戻ってきたのだ。 彼は私を捨てて彼女のもとへ行き、さらに私たちの最初の仔狼を死に追いやった。 けれど彼は気にも留めず、「いつかまた次の仔狼が生まれる」と言った。 しかし彼は知らない。私はすでに銀毒症に侵されており―― あと66日で死んでしまうのだ。
目次
第1章裏切りの記念日
「お前のような弱い狼は、ゴミでも食ってろ」
継父は、彼の精子にまみれた果物の皮を私に無理やり食べさせようとしていた。
私は全力でもがき、その魔の手から逃れようとしたが、両腕を折られてしまった。
涙が目に溢れ、心は恐怖と無力感で満たされる。
「やめろ!」
その時、聞き慣れた、けれど毅然とした声が響いた。
いつの間にか、一人の男が部屋の入り口に立っていた。その顔は怒りに満ちている。
強大なアルファだ!
継父は一瞬呆然とし、すぐに私を解放した。その目には、わずかな狼狽の色が浮かんでいた。
私はその隙に逃れ、よろめきながら彼の背後へ隠れ、小刻みに震えた。
「どうして自分の娘にこんなことができる!」
アレクサンダーは私の継父を睨みつけた。
継父は答えず、ただ私を一度だけ鋭く睨めつけると、家から出て行った。
私はアレクサンダーにきつく抱きついた。
彼は私の背中を優しく叩き、「もう大丈夫だ。彼が君を傷つけることは二度とない」と慰めてくれた。
その瞬間、私はこれまでに感じたことのない温もりに包まれた。
その後、私は望み通り彼――アレクサンダーのルナとなり、幸せは永遠に続くと信じていた。
だがその全ては、十周年の記念日に覆された。
彼の初恋の相手が、群れに帰ってきたのだ。
彼は私を捨てて彼女の元へ行き、私たちの最初の子狼を死なせた。
だが彼は気にしなかった。いつか次の子狼ができるだろう、と。
彼が知る由もなかったのは、私がすでに銀毒症に侵されていたことだ。
死まで、あと六十六日。
…………
今日は、私たちの結びつきを祝う記念日だというのに、私のアルファはなかなか家に帰ってこなかった。
テーブルに並べた、心を込めて準備したディナーを前に、私は不安げに自分のお腹を撫でていた。
腹の皮が擦れて少し腫れ上がるほど、その手は止まることがなかった。
アレクサンダーが帰宅したのは、零時を過ぎてからだった。
私は彼がどこへ行っていたのかを問い質すことなく、ただ微笑んで席に着くよう促した。
いつもとは違うテーブルの上のディナーを見て、彼は服を脱ぐ手を一瞬止めた。
私が食事を準備すると、彼はほんの数口食べただけでナイフとフォークを置いた。
「夕食は済ませてきた。君が食べるといい」
私は一つのギフトボックスを差し出した。中に入っているのは、一本の妊娠検査薬だ。
記念日に妊娠がわかるなんて、きっと月の女神からの贈り物に違いない。
私は期待に胸を膨らませて彼を見つめた。指が微かに震えている。
最近、私たちの関係はますます硬直していた。子狼の存在が、この状況を少しでも和らげてくれるかもしれない。
アレクサンダーは怪訝な顔で私を見た。
その視線がギフトボックスに落ち、彼はそれを受け取ろうと手を伸ばした。
アレクサンダーの指が箱に触れる寸前、彼の電話が鳴った。
「アレクサンダー、会いに来てくれない?」
女の声だった。
その聞き慣れた声で、私はすぐに相手が誰なのかを悟った。
アレクサンダーの初恋の相手、セリーナだった。
アレクサンダーの声は、優しく、そして切羽詰まっていた。「どこにいるんだ?」
彼は私を完全に無視し、背を向けてバルコニーへと歩いて行った。
その慌ただしい後ろ姿に、私の心は少しずつ沈んでいく。
電話の声は小さかったが、それでも彼らの会話は聞こえてきた。
「今朝あんなに強くしてきたから、すごく痛かった。まだ怒ってるんだから」
「あなたのルナといるのはやめて、こっちに来てよ」
「もし昔、彼女がいなかったら、今頃あなたのルナは私だったのに」
アレクサンダーはバルコニーに立ち、私に背を向けたまま、無意識に携帯電話の縁を指でなぞっていた。
私は息を殺したが、彼の返事は聞き取れなかった。
だが、彼の顔に浮かんだ甘やかすような笑みは、私の中にいる狼に悲痛な叫びを上げさせた。
私の伴侶は、私を裏切った。
私の中の狼は、それを知っていた。
私は手に持った妊娠検査薬の箱を強く握りしめ、爪が掌に食い込むほどだった。
胃の痙攣が、私を現実に引き戻す。
視線を戻そうとしたその時、アレクサンダーと目が合った。
私は何も言わず、ただ期待を込めた眼差しで彼を見上げた。
あの女を拒絶してくれることを、私は期待していた。
だが、現実は私を裏切る運命だった。
彼は私の視線を避け、「先に休んでいてくれ。少し出てくる」と低い声で言った。
私はその場に立ち尽くした。
アレクサンダーは私を一瞥もせず、もちろん私の手にあるギフトボックスを受け取ることもなかった。
彼は行ってしまった。
がらんとしたダイニングを見つめ、箱を握っていた手から力が抜けた。
この瞬間、心を込めて準備した贈り物は、まるで一つの冗談のようになってしまった。
十年経っても、アレクサンダーは私を愛してはくれなかった。
初恋の相手が帰ってきた瞬間、私は彼にあっさりと捨てられるゴミになったのだ。
おすすめ
/0/18682/coverbig.jpg?v=95d9cfce26ca3fdff284f2dbc9e3a0c9)
彼は私を捨てた——知らずに、財閥の娘を敵にして
香月しおり交際して3年目、江藤志年は私に隠れて、富豪令嬢の結城安奈と結婚した。 「知意、俺は私生児なんだ。彼女と結婚すれば、やっと父に認めてもらえる」 そんな言い訳、欲望の隠れ蓑にしか聞こえなかった。 私は潔く別れを告げた。けれど彼は、私を外の光が届かない場所に閉じ込めた。 「衣食住すべて揃った暮らしなんて、お前が一生かけても得られないだろ?何が不満なんだ」 それでも足りず、彼は令嬢を喜ばせるために、私に17階の屋上から飛び降りろと命じた。 私には何の力もないと思っていた彼ら。でも、知らなかったのね——私こそが、国一の大財閥の、たった一人の後継者だなんて。
/0/16912/coverbig.jpg?v=6094500432b1f7394a537c696ae01d2f)
離婚後、腹黒エリートの愛が止まらない
月城 セナ10年尽くした恋の終着点は、冷たい離婚届と嘲笑だった。 「跪いて頼めば、戻ってやってもいい」——冷泉木遠のその言葉に、赤楚悠はきっぱりと背を向ける。 三ヶ月後、世間が震えた。 彼女は世界的ブランド“LX”の正体不明のデザイナー、億を動かす実業家、そして…伝説の男・周藤社長に溺愛される女。 跪いて懇願する冷家に、彼女はただ一言。 「今の私は、あなたたちには高嶺の花すぎるの」 ——逆転と誇りに満ちた、爽快リベンジ・シンデレラストーリー!
/0/17655/coverbig.jpg?v=4a18214b7258b8ea5928ffc2966592e3)
契約妻は御曹司の独占愛に溺れる
桜宮 薫子お見合い当日、酔いに任せた“一夜の過ち”—— 相手は、都市一の権力を握る御曹司・沈川慎司。 逃げ出そうとした彼女に突きつけられたのは、まさかの「結婚宣言」!? こうして始まった契約結婚生活。 だけどこの夫、想像以上に甘くて強引。 仕事でも、恋でも、彼の独占欲は止まらない! 「噂ではゲイって聞いてたのに!」 「そんなの、信じちゃだめだよ——」 愛されすぎて困っちゃう、スパダリ系旦那との甘くて過激な新婚ライフ♡
/0/17001/coverbig.jpg?v=5d97059fc86a014da0e31371031a239e)
声を持たぬ妻は、愛を捨てた
瀬戸内 晴言葉を持たぬ妻・天野凜に、夫は五年間冷たいままだった。 子さえも奪われ、離婚後すぐに“忘れられない人”との婚約発表。 凜はその日、お腹の子を抱きながらようやく気づく——彼の心に、自分は一度もいなかったと。 すべてを捨て去り、沈黙の彼女は新たな人生へ。 だが、彼女を失ったその日から、男は狂ったように世界中を探し始めた。 再会の日、彼は懇願する。「頼む、行かないでくれ…」 凜は初めて声を発した。「——出ていって」
/0/17332/coverbig.jpg?v=ccb99d3220a8db315143e23210439794)
離婚したら、元夫が知らなかった私が目を覚ました
桜井 あんず「君なんて最初から必要なかった」 夫の冷たい一言で、榛名文祢の四年間の結婚は幕を閉じた。 家族のための政略結婚、心の中にいるのは宝木理紗だけ――そう告げられた彼女は、静かに立ち去る。 だが、去ったのは黒岩奥様であり、帰ってきたのは業界を震撼させる実力派カリスマ。 華やかな舞台で輝きを放つさくらを見て、前夫は戸惑い、嫉妬し、そして……気づく。 「君は最初から、誰よりも眩しかった」 けれどその隣には、すでに新たな男がいて——?
/0/17565/coverbig.jpg?v=b4b288b3ac9a609ecb7c6d4203eb3f02)
捨てられ妻、今は大物に抱かれています
霧生 隼裏切り、侮辱、離婚——それでも、柴田友子は再び立ち上がった。........ “ただの主婦”だった彼女は、いまや世界が注目する人気画家。 名声と輝きを手にした瞬間、かつての夫が「やり直そう」と現れる。 だが彼の視線の先には、さくらを腕に抱く謎の大物実業家の姿が―― 「紹介しよう。彼女は“俺の大切な人”だ」 嫉妬と未練、そして本当の恋が交差する、痛快逆転ラブロマンス。
トップ
 GOOGLE PLAY
GOOGLE PLAY
/0/19256/coverbig.jpg?v=ed320eb23fd59f03f55d53b79d8f30d2)