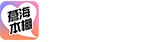私は「システム」に命じられ、ある本の世界にやってきた。ターゲットの「彼」を攻略するために。 もし彼に愛されなければ、私はシステムによって抹殺されてしまう。 全身がゆっくりと腐り果て、爛れていき、最後には骨の一片すら残さずに、一筋の血の水と化す……。 命のカウントダウンが終わりを告げる数日前、私は彼に伝えた。「もうすぐ死ぬの。だからお願い、少しだけでいいから私を愛して」と。 彼は冷たく言い放った。「それなら、死ねばいい」 ……それなのに。私が本当に死の淵に立ったとき、彼は泣きながら私に生きてくれと懇願するのだった。
目次
第1章私が消える前に、一度だけ愛してくれない?
私は、システムによって一冊の本の中からこの世界へ転送され、温久言を攻略するという使命を課せられた。
もし、彼を私に惚れさせることができなければ、待っているのはシステムによる「抹殺」だ。
全身がゆっくりと腐り果て、悪臭を放ち、最後には骨一本残さず血の海と化す、そんな無残な最期である。
生命のカウントダウンが残りわずかとなった日、私は彼に告げた。もうすぐ死ぬから、一度だけでいい、私を愛してほしい、と。
彼は冷たく言い放った。「だったら、さっさと死ねばいい」
そして私が本当に死の淵を彷徨った時、彼は泣きながら私に生きてくれと懇願した。
【1】
私の命は、刻一刻と終わりに向かっている。いつ砕け散ってもおかしくないこの身体を、毎日薬で無理やり繋ぎ止め、三日に一度は救命救急室に運び込まれるような有様だった。
病院のベッドに横たわりながら、点滴の針が刺さっていない方の手でスマートフォンを手に取り、温久言に電話をかけた。
彼が電話に出た瞬間、まるで甘いお菓子をようやく手にできた幼子のように、私の心は躍った。
「久言、また救命救急室に運ばれたの。でも、今回も大丈夫だった……」
「病院に来て、会ってくれない?」
救命処置を受けるたびに、私は温久言に電話をかける。たとえ声を聞くだけでも、張り詰めた心と身体が少しだけ和らぐ気がしたからだ。
「許渺然、お前は先月十七回、今月は八回も救命室に担ぎ込まれたそうだな。まだ死にきれていなかったのか?」
「同情を引くために、そんな陳腐な嘘をでっち上げるとは。大した執念だ」
やはり、温久言は私の言葉を信じていない。
だが、驚いたことに、彼は私が救命室に運ばれた回数を正確に覚えていた。
冷たい医療機器に何度命を呼び戻されたかなど、私自身ですら覚えていないというのに。
ただ一つ確かなのは、死の淵を彷徨うたび、私の脳裏に浮かぶのはいつも温久言の顔だったということ。
もし、彼が私を愛してくれたなら……。
私は本の中から生まれた、誰かの筆によって生み出された登場人物に過ぎない。私の運命は、とうの昔に定められている。
その運命を覆す唯一の方法が、この世界で温久言の愛を手にいれることだった。
もし彼が私を愛さなければ、私はただ無価値なまま、この身が塵と消える日まで、へりくだって生きるしかない。
「久言、私、本当に死ぬの」
「もう、いつまで持つかわからない。私が消える前に、もう一度だけ会ってくれないかな?」
「あなたの誕生日も、もうすぐでしょう?お祝いさせてほしいの」
私の声は、自分でも哀れに思うほどみすぼらしく震えていた。
スマートフォンの向こうから、温久言の冷笑が聞こえる。「死にたいならさっさと死ね!」
「お前が本当に息を引き取ったら、死体を片付けてやるくらいは考えてやってもいい」
一方的に電話は切られ、かけ直しても、彼のスマートフォンは電源が落とされていた。
目に涙が滲み、虚ろな瞳はただスマートフォンの黒い画面を映すだけだった。
攻略対象に本気で恋に落ちるなんて、とんだ間抜けだ。心のどこかで、自分を嘲笑う声がした。
【2】
温久言が会いに来てくれないのなら、私から会いに行けばいい。
彼の誕生日はもうすぐだ。どうせこの身体は治らないのだからと、私は退院手続きを済ませ、彼の誕生日を祝う準備をすることにした。
病院を去る前、主治医が私に言った。「今のあなたの身体では、病院で化学療法を続けなければ、半月も持たないかもしれません」
「大丈夫です」と私は微笑んだ。「いずれ来る日なら、いっそ家に帰って、旅立ちの準備をしようと思いまして」
医師は同情的な眼差しを私に向けた。「あなたも不憫な方だ。一ヶ月以上も入院していて、ご家族は一度もお見えにならなかった」
「ご主人は一度いらっしゃいましたが、あなたを罵ってすぐに帰ってしまわれたし……」
医師は言い淀み、言葉に詰まった末、長いため息を漏らした。
彼女が何を言いたいのかは分かっていた。私の夫である温久言はなんて非道い男なのだ、と。
私の家族はなんて冷酷なのだ、と。
だが、彼女は知らない。私がそもそも、泡のように儚い存在で、家族などいないということを。
温久言だけが、私の唯一の家族だった。
本の世界から弾き出されたばかりの、ぼろぼろだった私を拾ってくれたのは彼だった。
彼は私に許渺然という名を与え、文字の読み書きを教えてくれた。
そして、何不自由ない暮らしと、穏やかな日々を与え、献身的に私を世話してくれたのだ。
だから、彼を攻略することなど、きっと簡単なはずだと思っていた。
しかし、ある偶然がすべてを変えた。彼が友人の悪戯で薬を盛られ、理性を失った時、私は自ら彼の解毒剤となった。
翌朝、彼が正気を取り戻した後、私は恥じらいながら彼の胸に寄り添い、言った。「温久言、私はもうあなたのものよ。私たち、付き合いましょう」
だが、彼は私を突き放した。「人の弱みに付け込むとは!恥知らずめ!」
私はベッドから転がり落ち、呆然と彼を見上げた。「あなたも私のことを好きじゃなかったの?どうして怒るの?」
彼は服を着ながら、私に向かって吼えた。「俺の心には蘇月月しかいない。お前なんて、道端で拾ったただの物乞いだ。好きになるわけがないだろう!」
その時初めて、温久言が私を好きではないのだと知った。
あの日を境に、彼は私を嫌い始めた。
だがその後、私たちの関係が彼の両親に知られ、無理やり結婚させられることになった。
彼が私に向ける感情は、嫌悪から憎悪へと変わっていった。
おすすめ
/0/19057/coverbig.jpg?v=6adf425183e50931146bf64836d3c51d)
捨てられた妻の華麗なるざまぁ
山本 悠介彼女は、彼の深い愛情を信じてきた。そして、その裏切りもまた目の当たりにした。 彼女は目の前で結婚写真を燃やしたが、彼はただ携帯を抱えて愛人をあやすばかり。 ほんの一瞥すれば気づけたはずなのに、それすらしなかった。 ついに彼女の心は冷え切り、彼の頬を思い切り叩き、愛人との末永い幸せを祝ってやった。 そして振り返ることなく、閉鎖的な研究グループへの加入を申請し、すべての身分情報を抹消した――彼との婚姻関係さえも! ついでに、去り際に一つ“大きな贈り物”を残して。 グループに入った瞬間、彼女は姿を消し、彼の会社は破産の危機に追い込まれる。必死で彼女を探す彼の前に届いたのは、ただ一通の“死亡認定書”だった。 彼は崩れ落ちるように叫ぶ。「信じない、認めない!」 …… 再会のとき、彼は衝撃を受ける。そこに立つ彼女は、もはや別の名を持ち、隣には彼ですら仰ぎ見るほどの権力者がいた。 彼は縋るように懇願する。「俺が悪かった、戻ってきてくれ!」 しかし彼女は眉を上げ、優雅に微笑みながら隣の大人物の腕を取る。 「残念ね。今の私には、もうあなたなんて届かないわ」
/0/19325/coverbig.jpg?v=5ca1ca27d41583231a2b059d3695f96c)
元妻に跪く冷徹社長
朝霧 知恵三年前、彼女は周囲から嘲笑を浴びながらも、植物状態の彼と結婚するという固い決意を貫いた。 三年後、彼女が不治の病を患い、中絶を余儀なくされたその時、夫は別の女性のために、世間の注目を浴びながら大金を投じていた。 手術室から出てきた時、夫を深く愛していた彼女の心もまた、死んだ。「あなた、離婚しましょう!」 離婚すれば他人同士。彼はきらびやかな女性関係を、自分は残された人生を謳歌する。 そう思っていたのに―― 「俺が悪かった。帰ってきてくれないか?」 冷徹で気高かったはずの元夫が、プライドを捨てて元妻の前にひざまずく。「頼むから、俺のそばに戻ってきてくれ」 彼女は差し出された薔薇を冷たく突き放し、胸を張って言い放った。「もう遅いわ!」
/0/17451/coverbig.jpg?v=b6704e32b9abf8fe5a82110c88522c4e)
「さよなら」を告げたのは、あなたよ?
白鳥 あおい一度は彼にすべてを預けた――若く無防備だった津本薫は、愛よりも欲望にまみれた関係にすがっていた。 だが彼の心にいたのは、帰ってきた“昔の恋人”。 空っぽの部屋、無言の夜、そして別れの言葉と一枚の小切手。 「後会うこともないわ」 彼女はそう言って、涙一つ見せずに立ち去った。 ……数年後、再会した彼女の隣には新たな男性が。 嫉妬に焦がれた彼は、億の財産と指輪を差し出して告げる―― 「列に並ばず、もう一度君のそばにいたい」
/0/17332/coverbig.jpg?v=ccb99d3220a8db315143e23210439794)
離婚したら、元夫が知らなかった私が目を覚ました
桜井 あんず「君なんて最初から必要なかった」 夫の冷たい一言で、榛名文祢の四年間の結婚は幕を閉じた。 家族のための政略結婚、心の中にいるのは宝木理紗だけ――そう告げられた彼女は、静かに立ち去る。 だが、去ったのは黒岩奥様であり、帰ってきたのは業界を震撼させる実力派カリスマ。 華やかな舞台で輝きを放つさくらを見て、前夫は戸惑い、嫉妬し、そして……気づく。 「君は最初から、誰よりも眩しかった」 けれどその隣には、すでに新たな男がいて——?
/0/19545/coverbig.jpg?v=edd8f2129eba477569eaa05e01023bd3)
出所した悪女は、無双する
時雨 健太小林美咲は佐久間家の令嬢として17年間生きてきたが、ある日突然、自分が偽物の令嬢であることを知らされる。 本物の令嬢は自らの地位を固めるため、彼女に濡れ衣を着せ陥れた。婚約者を含む佐久間家の人間は皆、本物の令嬢の味方をし、彼女を自らの手で刑務所へと送った。 本物の令嬢の身代わりとして4年間服役し出所した後、小林美咲は踵を返し、東條グループのあの放蕩無頼で道楽者の隠し子に嫁いだ。 誰もが小林美咲の人生はもう終わりだと思っていた。しかしある日、佐久間家の人間は突然気づくことになる。世界のハイエンドジュエリーブランドの創設者が小林美咲であり、トップクラスのハッカーも、予約困難なカリスマ料理人も、世界を席巻したゲームデザイナーも小林美咲であり、そしてかつて陰ながら佐久間家を支えていたのも、小林美咲だったということに。 佐久間家の当主と夫人は言う。「美咲、私たちが間違っていた。どうか戻ってきて佐久間家を救ってくれないか!」 かつて傲慢だった佐久間家の若様は人々の前で懇願する。「美咲、全部兄さんが悪かった。兄さんを許してくれないか?」 あの気品あふれる長野家の一人息子はひざまずきプロポーズする。「美咲、君がいないと、僕は生きていけないんだ」 東條幸雄は妻がとんでもない大物だと知った後、なすがままに受け入れるしかなくなり…… 他人から「堂々とヒモ生活を送っている」と罵られても、彼は笑って小林美咲の肩を抱き、こう言うのだった。「美咲、家に帰ろう」 そして後になって小林美咲は知ることになる。自分のこのヒモ旦那が、実は伝説の、あの神秘に包まれた財界のレジェンドだったとは。 そして、彼が自分に対してとっくの昔から良からぬことを企んでいたことにも……
/0/16915/coverbig.jpg?v=89ed53f6c82d5aef26b777477a92c084)
追い出された果てに、億の愛が始まる
藤宮 あやね20年間尽くした水野家に裏切られ、追い出された恩田寧寧。 「本当の親は貧乏だ」——そう思われていたが、その実態は海城一の名門。 億単位の小遣いに、百着のドレスと宝石、そして溺愛されるお嬢様生活。 彼女を侮っていた“元・家族”たちは、次々と彼女の真の素顔に震撼する—— 世界一の投資家、天才エンジニア、F1級のレーサー!? そんな彼女を捨てた元婚約者が、なぜか突然「やっぱり好きだ」と告白? でももう遅い——“本物の兄”とのお見合いが始まってるのだから。
トップ
 GOOGLE PLAY
GOOGLE PLAY
/0/19497/coverbig.jpg?v=4dfb9fc29e50e0eec3c1edf56e72e565)