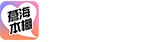家が洪水に沈んだ時、兄と夫は二人ともアリスを選んだ。 つい最近、一族に探し出されたばかりのお嬢様である。 私の右脚は、彼女が故意に激しくぶつかってきたせいで骨折した。 救出された時、目にしたのは夫の胸に飛び込んでしゃくり上げるアリスの姿だった。 「さっき、お姉様がずっと私を押さえつけて、洪水の中で殺そうとしてきたの」 その言葉を聞き、夫と兄は苦々しい顔で担架に横たわる私を見下ろした。 「リサ、お前はアリスの人生を長年奪っておきながら、今度は殺そうとまでしたのか!」 兄は私をあざ笑い、夫は痛ましげにアリスを腕の中に庇った。 二人は何事か囁き合うと、そばにあった砕石を手に取り、こちらへ歩み寄ってきた。 「リサ、どうやら我々はお前を長年甘やかしすぎたようだな」 「まさかこれほど悪辣な人間になっていたとは」 「その脚を一本折って、骨身に刻ませてやろう」 彼らの獰猛な形相は、まるで知らない人のようだった。 私は必死に抵抗したが、力ずくで押さえつけられた。 彼らが手にした石を振り上げ、私の脚めがけて振り下ろそうとしたその瞬間、私は目を閉じた。 私は、ここを離れる。 絶対に、ここを離れてみせる!
目次
第1章砕かれた旋律
家が洪水に飲み込まれた時、兄と夫はどちらもアリスを選んだ。
カンター家にようやく探し出された、本当の令嬢である彼女を。
彼女が故意に突き飛ばしてきたせいで、私の右足は折れていた。
救助された時、夫の腕の中に飛び込んでしゃくり上げるアリスの姿が見えた。
「お姉様がずっと私を押さえつけて、洪水で死なせようとしたの」
その言葉を聞き、夫と兄は担架に横たわる私を険しい顔で見下ろした。
「リサ、お前は長年アリスの人生を奪っておきながら、今度は彼女を殺そうとまでしたのか!」
兄は私を嘲笑し、夫は痛ましげにアリスを腕の中に庇った。
二人は何か言葉を交わすと、傍らにあった瓦礫を手に取り、私へと歩み寄ってきた。
「どうやら我々は、長年お前を甘やかしすぎてしまったようだな、リサ」
「これほど悪辣な人間になってしまうとは」
「その足一本を折って、思い知らせてやろう」
鬼のような形相の彼らは、まるで別人のようだった。
必死にもがいたが、体は力ずくで押さえつけられる。
彼らが瓦礫を振り上げ、私の足に叩きつけようとした瞬間、私は目を閉じた。
ここから去らなければ。
絶対に、去らなければならない――!
……
「ああ!」
苦痛がふくらはぎから脳天を貫いた。
ロバートが拳大の瓦礫を握りしめ、
私の足に何度も、何度も叩きつけている。
すでに折れていた足は肉が裂け、白い骨が覗いていた。
骨が砕ける激痛に、全身が痙攣する。
私は絶叫し、身をよじった。
「やめて!私は彼女を殺そうなんてしていない!」
アリスの体には傷一つないというのに、私の家族と愛する人は、いとも容易く彼女の言葉を信じた。
ジョンは私の弁明に耳を貸さず、ただ靴先で私の指を執拗に踏みつけ、逃れようとする体を押さえつけた。
全体重をかけた一撃。十指は心に通ずると言うが、まるで心臓を鋭い棘で突き刺され、引き抜かれたかのようだった。
血の川が広がる。
「リサ、嘘までつくようになったのか」
夫が失望の色を浮かべて私を見る。
反論したかったが、涙で視界が滲んだ。
指を砕かれた。これで、もうピアノは弾けないのだろうか?
最後の力を振り絞って顔を上げると、アリスの得意げな瞳と目が合った。
「必ず、報いを受けさせる」
私は一言一言、そう告げた。
そして、激痛の中で意識を失った。
医師の診察を受ける気配で目を覚ました。
足と手には、分厚く包帯が巻かれている。
恐ろしいことに、自分の足の感覚が全くなかった。
私は恐怖に怯えながら医師を見つめたが、唇が震えるだけで声が出ない。
医師は首を横に振った。「お嬢さん、あなたの足の状態は芳しくありません。我々は全力を尽くします」
「手は……私の手はどうなんです?」
掠れた声で、私は叫んだ。
「もう一度、ピアノを弾くことはできますか?」
医師はため息をついた。
「リサさん、手の怪我自体は深刻ではありません。しかし、今後、常に震えが残ることになるでしょう。長時間ピアノの練習をするのは、もう難しいかもしれません」
私は呆然と医師を見つめ、信じられないとばかりに首を振った。
そんなことが許されていいはずがない!
幼い頃からピアノ一筋に生きてきて、今では名の知れたピアニストにまでなったというのに。
それなのに、もうピアノが弾けない?
そして、その全てを引き起こしたのが、私の家族――ずっと私を可愛がってくれた、最愛の兄だなんて!
医師は痛ましげに顔を背けて去っていった。病室の外から、ひそひそと噂話が聞こえてくる。
「あのお嬢さんも気の毒に。怪我をしてから誰も見舞いに来ないなんて」
「気の毒なものか。嫉妬から人を殺そうとして、返り討ちにあったって話だぞ」
「だとしたら自業自得だな。当然の報いだ」
そうか、外ではそんな風に噂されていたのか。
心臓をナイフで抉られ、血が一滴一滴したたり落ちるようだった。
あの人たちは真実を確かめようともせず、アリスの言葉だけを信じたのだ。
その時、甘ったるい声が不意に耳元で響いた。
アリスだった。笑みを浮かべて私の前に現れ、憐れむような素振りをしながらも、その瞳には隠しきれない得意の色が浮かんでいた。
「お姉様、たいした怪我でもないのに、まだ仮病を使っているの?」
そう言いながら、彼女は私の負傷した足に軽く触れた。
鋭い痛みが全身を駆け巡る。 私は歯を食いしばって彼女を睨みつけ、低い声で尋ねた。
「どうしてこんなことを?」
アリスの美しい瞳は、今や毒々しい憎悪に満ちていた。
「どうしてですって? あの時あなたのせいで、 私がどれだけ外で苦労したと思っているの?!」
私は眉をひそめて彼女を見つめ、訳が分からずに問い返した。
「どういう意味?」
「あなたがわざと私を病気にしたせいで、私はカンター家に戻れなかったじゃない!全部あなたのせいよ!」
アリスは私の腕に強く爪を立て、その指先が肉に深く食い込んだ。
彼女が病気になったことと、私に何の関係があるというのだろう?
彼女を突き放そうと手を伸ばした。
すると彼女は突然床に倒れ込み、悪意に満ちた笑みを浮かべながら、自らの頬を平手で打ちつけた。
朝霧 知恵のその他の作品
もっと見る/0/19620/coverbig.jpg?v=6048ba0c30b268a17a02fca2c3dd18f5)
叔父様、その愛は罪ですか?
都市10歳の年、孤児だった彼女は、とある名家の養女となった。 肩身の狭い暮らしの中、義理の叔父が彼女の人生における一筋の光となる。 しかし人の心は移ろいやすいもの。彼は突然、彼女を置いて海外へ行ってしまった。 7年ぶりの再会は、ある葬儀の場だった。彼女はまるで何かに導かれるように、彼に誘惑されてしまう。 表向きは叔父と姪。しかしその実、彼女は彼の日陰の恋人だった。 名家同士の政略結婚が決まり、かつては遊び人だった男も、ついに婚約者の前では牙を抜かれたと誰もが噂した。 だが、世間で言う「愛妻家」の彼が、どれほど奔放で裏表の激しい男かを知っているのは、彼女だけだった。 彼に腰を掴まれ壁に押し付けられた彼女は尋ねる。「婚約者さんが嫉妬するんじゃない?」 彼は彼女の耳たぶを噛み、囁いた。「彼女には気づかせない」 共に過ごす日々の中、彼女は彼を愛してしまった。涙ながらに彼に懇願する。「私と結婚して」 彼は冷たい顔で彼女の服を直し、言い放った。「君と結婚することは、生涯ない」 後日、彼女は別の男性からの求婚を受け入れた。名家の養女と法律事務所のパートナーが結ばれるという吉報は、街中に広まった。 しかし、結婚式当日、彼は彼女の前にひざまずき、懇願した。──どうか、嫁に行かないでくれ、と……。
/0/19325/coverbig.jpg?v=5ca1ca27d41583231a2b059d3695f96c)
元妻に跪く冷徹社長
都市三年前、彼女は周囲から嘲笑を浴びながらも、植物状態の彼と結婚するという固い決意を貫いた。 三年後、彼女が不治の病を患い、中絶を余儀なくされたその時、夫は別の女性のために、世間の注目を浴びながら大金を投じていた。 手術室から出てきた時、夫を深く愛していた彼女の心もまた、死んだ。「あなた、離婚しましょう!」 離婚すれば他人同士。彼はきらびやかな女性関係を、自分は残された人生を謳歌する。 そう思っていたのに―― 「俺が悪かった。帰ってきてくれないか?」 冷徹で気高かったはずの元夫が、プライドを捨てて元妻の前にひざまずく。「頼むから、俺のそばに戻ってきてくれ」 彼女は差し出された薔薇を冷たく突き放し、胸を張って言い放った。「もう遅いわ!」
おすすめ
/0/17332/coverbig.jpg?v=ccb99d3220a8db315143e23210439794)
離婚したら、元夫が知らなかった私が目を覚ました
桜井 あんず「君なんて最初から必要なかった」 夫の冷たい一言で、榛名文祢の四年間の結婚は幕を閉じた。 家族のための政略結婚、心の中にいるのは宝木理紗だけ――そう告げられた彼女は、静かに立ち去る。 だが、去ったのは黒岩奥様であり、帰ってきたのは業界を震撼させる実力派カリスマ。 華やかな舞台で輝きを放つさくらを見て、前夫は戸惑い、嫉妬し、そして……気づく。 「君は最初から、誰よりも眩しかった」 けれどその隣には、すでに新たな男がいて——?
/0/19545/coverbig.jpg?v=edd8f2129eba477569eaa05e01023bd3)
出所した悪女は、無双する
時雨 健太小林美咲は佐久間家の令嬢として17年間生きてきたが、ある日突然、自分が偽物の令嬢であることを知らされる。 本物の令嬢は自らの地位を固めるため、彼女に濡れ衣を着せ陥れた。婚約者を含む佐久間家の人間は皆、本物の令嬢の味方をし、彼女を自らの手で刑務所へと送った。 本物の令嬢の身代わりとして4年間服役し出所した後、小林美咲は踵を返し、東條グループのあの放蕩無頼で道楽者の隠し子に嫁いだ。 誰もが小林美咲の人生はもう終わりだと思っていた。しかしある日、佐久間家の人間は突然気づくことになる。世界のハイエンドジュエリーブランドの創設者が小林美咲であり、トップクラスのハッカーも、予約困難なカリスマ料理人も、世界を席巻したゲームデザイナーも小林美咲であり、そしてかつて陰ながら佐久間家を支えていたのも、小林美咲だったということに。 佐久間家の当主と夫人は言う。「美咲、私たちが間違っていた。どうか戻ってきて佐久間家を救ってくれないか!」 かつて傲慢だった佐久間家の若様は人々の前で懇願する。「美咲、全部兄さんが悪かった。兄さんを許してくれないか?」 あの気品あふれる長野家の一人息子はひざまずきプロポーズする。「美咲、君がいないと、僕は生きていけないんだ」 東條幸雄は妻がとんでもない大物だと知った後、なすがままに受け入れるしかなくなり…… 他人から「堂々とヒモ生活を送っている」と罵られても、彼は笑って小林美咲の肩を抱き、こう言うのだった。「美咲、家に帰ろう」 そして後になって小林美咲は知ることになる。自分のこのヒモ旦那が、実は伝説の、あの神秘に包まれた財界のレジェンドだったとは。 そして、彼が自分に対してとっくの昔から良からぬことを企んでいたことにも……
/0/19221/coverbig.jpg?v=1d5cb0078bd2cba9bb9bd183cc3c7440)
捨てられ主婦、正体は世界的カリスマ
木村 美咲織田七海は3年間、専業主婦として家を支え続けたが、その努力の末に待っていたのは元夫の冷酷な裏切りだった。 元夫は本命のために彼女を捨て、全都市中の笑いものにしたのだ。 しかし、元夫と別れてからの織田七海の人生は一変。隠していた正体が次々と明らかになり、その才能と魅力で世界中を驚かせる存在となる。 やがて、彼女が万能の大物であると気づいた元夫は後悔に駆られ、必死に追いかけ始める。ついにはダイヤの指輪を手に、片膝をついて彼女の前で懇願した。「七海、やり直そう!」 織田七海:「ふざけんな!!!」 高田宗紀は愛する妻をしっかりと抱き寄せ、冷ややかに告げる。「人違いだ、これが俺の妻だ。 それとお前は……誰か!そいつを外へ!川に放り込んで魚の餌にしろ!」
/0/17333/coverbig.jpg?v=ab8c582413ed19a11aae8a8cc2a391b3)
契約妻を辞めたら、元夫が泣きついてきた
藤宮 あやね冷徹な契約結婚のはずが、気づけば本気になっていた―― 藤沢諒との結婚生活で、神崎桜奈はただひたすらに尽くしてきた。 だが火災の夜、彼が守ったのは「初恋の彼女」。 心が砕けた彼女は静かに家を去り、すべてを捨てて離婚届に判を押す。 ……数ヶ月後、彼女は別人のように華やかに輝いていた。 恋敵たちが列をなす中、彼は懇願する。「君がいないとダメなんだ、やり直そう」 その言葉に、彼女は微笑む――「再婚希望?じゃあ四千万円から並んでね」
/0/16871/coverbig.jpg?v=41d448583624096a3538ad44241991a3)
小悪魔な君を、甘やかしたい――病み系社長の愛情攻撃
花園 みお裏切り、中傷、家族の崩壊、そして悲劇の最期。 白川南音の前世は、あまりにも残酷だった。 だが生まれ変わった今、彼女はもう騙されない。 恩?恋?同情?——そんなもの、全て捨てて構わない。 渾身の力で裏切り者を潰し、没落した一族を再興し、彼女は今度こそ人生を取り戻す。 そして再び出会ったのは、前世で唯一手の届かなかった男。 「前回は間に合わなかった。でも今度こそ、君を迎えに来た」 ——復讐と再生、そして予期せぬ愛が交錯する、逆転ヒロイン・ロマンス。
/0/18034/coverbig.jpg?v=63ff8b3a25ffd30a75f58fd39800ca48)
愛を諦めたあの日、彼はまだ私を手放していなかった
ぷに林めい結婚二年目、赤子を宿した白川明澄に届いたのは――離婚届。そして交通事故、流れる血の中で彼に助けを乞うも、腕に抱かれていたのは初恋の人だった。命と心を喪い、彼女は静かに目を閉じた。数年後、「白川明澄」という名は藤原誠司にとって禁句となった。彼女が他の男と結婚式を挙げるその日、彼は叫ぶ。「俺の子を連れて、誰と結ばれる気だ?」——愛は終わったはずだった。だが、終わらせたのは誰だったのか。
トップ
 GOOGLE PLAY
GOOGLE PLAY
/0/19886/coverbig.jpg?v=501a04fb7a34f51ed12090314938edfb)