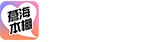我が家の屋根裏には、一匹の化け物が閉じ込められている。 その化け物とは、私の実の兄。両親がその手で閉じ込め、実に二十四年もの歳月が流れていた。 両親は私に、兄は頭がおかしく、極めて暴力的なので、他人を傷つけないように閉じ込めておくしかないのだと聞かせていた。 しかし、ある日誤ってその部屋に入ってしまった私に、兄は突然口を塞ぎ、怯えきった顔でこう告げたのだ。あの二人は、本当の両親じゃない、と。
目次
第1章屋根裏の怪物
我が家の屋根裏には、一匹の怪物が閉じ込められている。
この怪物は私の実の兄で、両親の手によってそこに閉じ込められ、実に二十四年もの歳月が流れていた。
両親は私に、兄は頭がおかしく、深刻な暴力傾向があるため、他人を傷つけないように閉じ込めておくしかないのだと説明した。
しかしある時、私が誤ってその部屋に入ってしまうと、兄は私の口をぐっと塞ぎ、恐怖に満ちた顔で、あの二人は本当の両親ではないと告げたのだ。
01
三歳の頃にはもう、我が家の屋根裏に怪物が閉じ込められていることを知っていた。
正確に言えば、それは私の兄だった。
しかし、物心ついた時から、私は一度も兄に会ったことがなかった。
兄はずっと屋根裏の小部屋に閉じ込められており、両親は兄が病気なのだと言った。
彼は理由もなく人を傷つけ、知能に障害があり、深刻な暴力傾向を持っている、と。
兄が外に出て他人を傷つけるのを防ぐため、両親は兄を屋根裏に閉じ込めるという選択をするしかなかった。
私は、両親が兄のことで人知れず涙を拭う姿を一度ならず見てきた。
食事時になると、いつも母か父が食事を運んでいき、私がその小部屋に行ったことは一度もなかった。
兄が怖かったからだ。
幼い頃からずっと、屋根裏からは鉄の鎖が引きずられる音と、兄が絶えず発する低いうなり声が聞こえてきた。
それはほとんど私の子供時代のトラウマとなっていた。
「兄」という言葉は、私にとって悪夢そのものだった。
私はどの友人にも、兄の存在を話したことはなかった。
その日、学校から帰ると両親は外出しており、食事は冷蔵庫にあるから温めて食べなさいと置き手紙があった。
電話口で母は、絶対に屋根裏へは行かないようにと何度も念を押した。
もちろん、彼女に言われなくても、私があそこへ行くはずがなかった。
私にとって、そこは禁じられた場所だった。
私は食事を温め、ドラマを見ながら食べ始めた。
突然、屋根裏から鎖が引きずられる音が聞こえてきた。
兄だ!
私は眉をひそめ、無視を決め込んだが、階上からは苦痛に満ちた叫び声まで聞こえてきた。
その声はあまりに苦しそうで、聞いている私の胸まで苦しくなった。
兄は体の具合でも悪いのだろうか?
兄のことは好きではなかったが、それでも血の繋がった家族だ。
私は心の中の恐怖を抑え、階段を上って屋根裏へと向かった。
屋根裏は非常に狭く薄暗く、赤い木の扉には錠前が掛かっていた。
鍵のありかは知っている。母はいつも私に見られないように隠していたが、私はこっそりと見てしまっていた。
私はつま先立ちで本棚から一冊の本を取り出し、その中に挟まれていた鍵を取り出した。
重苦しいうめき声が扉の向こうから漏れ聞こえ、鍵が錠前に差し込まれるのと同時に、私の心臓も速く鼓動し始めた。
ついに、扉が開いた。
十八年間、私は初めてこの部屋に足を踏み入れた。
顔をしかめるほどひどい匂いが、鼻をついた。むせ返るような悪臭に、私は何度か咳き込んだ。
そこには、手足に鉄の鎖を繋がれた一人の男がいた。男は髭も剃らず、伸び放題の髪が顔のほとんどを覆い隠していた。
これが、私の兄。血の繋がった肉親。
兄の姿を見た時、想像していたような恐怖はなく、むしろ涙がこみ上げてくる衝動に駆られた。
「お兄ちゃん?」 私は小声で呼びかけた。
兄は荒い息をつき、口を開けて、シュー、シューという音を立てた。
その時、私は兄が話せないのかもしれないと気づいた。
しかし、彼の眼差しは私を傷つけようとしているようには見えなかった。
私は恐る恐る近づいた。兄に近づけば近づくほど、あの不快な悪臭は強烈になる。
私は兄の前にしゃがみ込んだ。「お兄ちゃん、何か私に言いたいことがあるの?」
兄は頷き、その目からは、なんと一筋の涙が流れ落ちた。
私は紙とペンを探し出し、彼に手渡した。
しかし、兄の手は傷だらけで、ペンを握ることさえできなかった。
兄は苦心してペンを口にくわえ、紙に一行の言葉を書き記した。
「あの二人は、俺たちの本当の両親じゃない」
02
その言葉を見て、私は一瞬にして凍りついた。
しかし、兄にその意味を問い質す間もなく、階下から両親がドアを開ける音が聞こえた。
兄の目に恐怖と混乱の色が浮かび、彼は視線で早く行くようにと私に合図した。
私は慌てて紙とペンを持って部屋を飛び出し、扉に鍵をかけ、鍵を元の場所に戻した。
両親が階段を上ってくる足音が聞こえ、私は急いで本棚の陰に隠れた。
幸い、両親は私に気づかず、鍵を取り出して扉を開けた。
彼らは食事を手に中へ入っていき、中からは再び兄のうなり声が響き渡った。
二人が出てくる前に、私は急いで階下へ駆け下り、トイレに隠れた。そして、ちょうどトイレから出てきたかのように装った。
母は私を見ると、にっこりと笑った。「何を買ってきたと思う?」
母の視線の先、テーブルの上には、私の大好物であるティラミスが置かれていた。
この十八年間、両親は外出するたびに、私の好きなケーキを忘れずに買ってきてくれた。
彼らの私への気遣いは、至れり尽くせりと言ってよかった。
幼い頃、一度三十九度の熱を出した時、母が三日三晩、つきっきりで看病してくれたことを覚えている。
こんなにも私を愛してくれる両親が、偽物であるはずがない。
しかし、兄の言葉が私の心に疑念の種を蒔いていた。
私は何でもないふりを装い、ケーキを食べながら、さりげなく尋ねた。「お母さん、小さい頃の、家族三人の写真ってある?」
母は笑って言った。「もちろんあるわよ。毎年家族写真を撮りに行ってたの忘れたの?ただ、あなたの可哀想な兄さんは……」
そう言うと、母は目を赤くした。
「私が言ってるのは、三歳より前の家族写真のこと」 私はゆっくりと言った。
母は驚いたように私を見た。「若若、どうして急にそんな昔の写真が見たくなったの?」
「最近、先生がテーマ別のHRを開くことになって、みんな小さい頃からの家族写真を持ってこなきゃいけないの!」 私は適当な理由をでっち上げた。
母は困ったように言った。「あなたが三歳になる前は、うちが一番家計が苦しかった時期なのよ。あの頃はカメラを買うお金なんてなかったわ」
私の心は沈んだ。
私が物心ついたのは三歳の時で、その頃の両親の姿は脳裏に焼き付いている。
しかし、よりにもよって三歳より前の家族写真がないのでは、兄の言葉が真実か嘘か、確かめようがない。
その時、父が深いため息をついて言った。「若若、お兄ちゃんの病気はますますひどくなっている。ここ数日、外に出たいがために、支離滅裂な嘘をでっち上げるようになったんだ」
「このところ、ずっとお兄ちゃんを治してくれるお医者様を探しているの。お母さんもお父さんも、将来あの子があなたの重荷にならないようにしたいのよ」 母は目を赤くしながら言った。
私の心は乱れていた。
会ったばかりの兄よりも、十八年間私を育ててくれた両親の方を信じたい。
彼らが私に注いでくれた愛情は、本物だった。
ケーキを食べ終え、私は部屋に戻り、上の空で問題集を解いていた。
来年は、私にとって極めて重要な一年になる。
しかし、私の脳裏からは、兄のあの苦痛に満ちた眼差しがどうしても離れなかった。
ノックの音がして、母が牛乳を一杯持って入ってきた。
「若若、一生懸命なのはわかるけど、ちゃんと休憩もとりなさい」 母は私の机に牛乳を置いた。
ケーキを食べたばかりでまだお腹がいっぱいだったため、今はあまり牛乳を飲みたくなかったが、母はそこに立ったまま、じっと私を見つめている。
「若若、冷めないうちに早く飲みなさい。お母さんがカップを洗いに行くから」
その眼差しは、どこか切迫しているようだった。
私ははっとした。思えば以前から母はいつもこうやって、私が牛乳を飲み干すのを待ちきれない様子で見つめていた。
「お母さん、そこに置いといて。後で飲むから」
母は不承不承といった様子で部屋を出ていったが、去り際に、必ず牛乳を飲むようにと何度も念を押した。
私の心に、この牛乳には何か問題があるのではないか、という考えがふとよぎった。
しかし、すぐにその考えを打ち消した。もう十何年も飲み続けているのだ。もし問題があるなら、とっくに何か起きているはずだ。
私は牛乳を手に取り、飲もうとしたその時、ふと視界の端に、ドアが少しだけ開いているのが映った。
振り返ると、母が蒼白な顔でドアの隙間に張り付き、無表情で私を見ていた。
03
「お母さん、何してるの?」 私は驚いて思わず声を上げた。
母は気まずそうに笑みを浮かべた。「あなたが牛乳を飲まないと、栄養が偏るんじゃないかと思って」
母のその態度は、かえって牛乳への疑念を深めさせた。
「お母さん、もうこんなに大きいんだから、そんなに心配しないで」 私はため息交じりに言った。
「わかったわ。でも、必ず飲むのよ」 母はそう言い残して去っていった。
私の心臓は激しく鼓動していた。すぐに牛乳をトイレに流した。
深夜、両親が寝静まったのを見計らい、私は再び屋根裏へと向かった。
抜き足差し足で鍵を開けると、兄は私を見て、ひどく興奮した様子だった。
兄の前には、まだ片付けられていない、今日母が持ってきたばかりの食事が置かれていた。
その料理を見て、私は心底驚愕した。
それは、私たちが食べ終わった残飯や残り物で、すべてがごちゃ混ぜにされ、不快な匂いを放っていた。
私が食べていた温かく美味しい食事と、兄が食べているこの豚の餌にも等しいものを思うと、私の鼻の奥がツンとした。
どうして両親は兄にこんな仕打ちができるのだろう?
まさか、兄の言ったことはすべて本当なのだろうか?
「お兄ちゃん、父さんや母さんはいつもこんなものをあなたに?」 私は耐えきれずに言った。
兄は黙ったままだったが、それが答えであることはわかった。
成人男性であるはずの兄の腕は、私のものよりも細く、衰弱していた。
私はペンを兄の前に差し出した。真実が知りたい。
もしあの二人が本当の両親でないのなら、私の本当の両親はどこへ行ってしまったのだろう?
兄は苦しげにペンを口にくわえ、紙に歪んだ文字を書き連ねた。
「あの二人は、俺たちの両親を殺したんだ。お前がまだ二歳の時にな」
その言葉に、私は心臓が跳ね上がるほどの衝撃を受け、信じることができなかった。
「その時、俺は八歳だった。俺は奴らの顔を見てしまったんだ。だから奴らは、俺に病気の汚名を着せて、ずっとここに閉じ込めてきた」
「俺たちの母方の祖父が、ずっと前に銀行に莫大な資産を預けてくれていた。銀行は毎月決まった額を送金してくる。奴らはその金には手を出せない。だから俺たちを生かしておいたんだ。だが、もしお前に万が一のことがあれば、奴らは銀行に行ってその金を引き出せるようになる」
「奴らがくれるものは、飲み物も含めて、絶対に口にするな。きっと、遅効性の毒が盛られている」
一行一行、歪んだ文字が、恐ろしい事実を突きつけてくる。
兄は、その骨張った手を伸ばし、私の肩を掴んだ。
彼の眼差しは、固く、力強かった。
「お前が先手を打つんだ。あの二人を殺して、父さんと母さんの仇を討て」
それが、兄が紙に書いた最後の言葉だった。
まさにその時、階下でドアが開く音が聞こえた。
美雨の風のその他の作品
もっと見る/0/19674/coverbig.jpg?v=0a3f43cea9f11988b39b2ded6b1d9d0a)
その令嬢、離婚につき正体を脱ぐ
都市【離婚後+正体隠し+元夫の激しい後悔+本物と偽物のお嬢様+スカッと痛快ラブ】 蕭明隼人が交通事故で失明した時、街中の令嬢たちは彼を避けていた。そんな中、明石凛だけが、ただ一人ためらうことなく彼に嫁いだ。 三年後、蕭明隼人の視力は回復する。彼はかつて想いを寄せた女性を喜ばせるためだけに60億の宝飾品を競り落とすが、明石凛に突きつけたのは一枚の離婚届だった。 彼は言う。「俺と秋子は、君のせいで何年もすれ違ってきた。もう彼女を待たせたくない!」 明石凛は、あっさりとサインをした。 誰もが彼女を笑いものにしていた。 庶民の娘が玉の輿に乗って蕭明家に嫁いだと笑い、そして今、お払い箱になった惨めな棄婦だと嘲笑っていた。 だが、誰も知らない。蕭明隼人の目を治療した名医が彼女であったことを。60億の宝飾品のデザイナーが彼女であったことを。株式市場を支配する投資の神様が彼女であったことを。トップクラスのハッカーが彼女であったことを……。そして、大統領家の本物の令嬢もまた、彼女であったことを! 後悔に苛まれる元夫は、ひざまずいてプロポーズする。「凛、もう一度だけチャンスをくれないか?」 とある俺様社長が、彼を叩き出す。「よく見ろ!彼女は俺の妻だ!」 明石凛:「……」 まったく、千年の鉄樹に花が咲くなんて!
/0/19431/coverbig.jpg?v=79afd0a2b3487b0d41e796c4b1cc369d)
義父に奪われた花嫁 ―禁断の契約婚―
都市卒業パーティーの夜、彼女は姉の策略にはめられ、見知らぬ男のベッドに送られてしまう。 三年間付き合った恋人には捨てられ、家族は重い病に倒れ、逃げ場を失った彼女は、やむなく放蕩息子との結婚を受け入れる。 その養父はわずか33歳にして市の頂点に立つ、街で最も若き大富豪。 残酷で暴虐な性格だと噂され、周囲は口を揃えて「彼女の人生は終わった」と囁いた。 だが実際には、養父はこの新しい嫁を溺愛した。 彼女を傷つけた者はすべて報いを受け、果ては実の息子さえ病院送りにされた。 こうして彼女には2つの秘密ができる。――一夜を共にした男は新郎の養父だったこと。――そして、自分がその男に恋をしてしまったこと。 やがて真実が明るみに出ると、男は一夜にして彼女への愛情を引き、洪水のごとく忌み嫌うようになる。 心が折れた彼女は、別の男からの求愛を受け入れる。 しかしデート当日、彼は彼女を連れ戻し、血走った目で言い放つ。「……俺だけを愛すると言ったよな? 戻ってきてくれ、頼む」 彼女は顎を指で持ち上げ、艶やかに微笑む。「遅すぎるのよ。今さら追いかけるなら、並んでもらわなきゃね……パパ」 「……」
おすすめ
/0/19031/coverbig.jpg?v=d4739ef41abb58baa114c66a1e004b54)
捨てられ花嫁、隣の席で運命が動き出す
高橋 結衣婚礼の席、新郎は星川理緒を置き去りにし、本命を追って去ってしまった。 その隣の会場では、花嫁が新郎が車椅子に乗っていることを理由に結婚を拒み、姿を見せなかった。 車椅子に座るその新郎を見て、星川理緒は苦笑する。 ──同じ境遇なら、いっそ一緒になってもいいのでは? 周囲からの嘲笑を背に、星川理緒は彼のもとへと歩み寄る。 「あなたは花嫁がいない。私は花婿がいない。だったら、私たちが結婚するっていうのはどうかしら?」 星川理緒は、彼が哀れな人だと思い込み、「この人を絶対に幸せにしてみせる」と心に誓った。 …… 結婚前の一之瀬悠介「彼女が俺と結婚するのは、金が目当てに決まってる。用が済んだら離婚するつもりだ。」 結婚後の一之瀬悠介「妻が毎日離婚したがってる……俺はしたくない。どうすればいいんだ?」
/0/17001/coverbig.jpg?v=5d97059fc86a014da0e31371031a239e)
声を持たぬ妻は、愛を捨てた
瀬戸内 晴言葉を持たぬ妻・天野凜に、夫は五年間冷たいままだった。 子さえも奪われ、離婚後すぐに“忘れられない人”との婚約発表。 凜はその日、お腹の子を抱きながらようやく気づく——彼の心に、自分は一度もいなかったと。 すべてを捨て去り、沈黙の彼女は新たな人生へ。 だが、彼女を失ったその日から、男は狂ったように世界中を探し始めた。 再会の日、彼は懇願する。「頼む、行かないでくれ…」 凜は初めて声を発した。「——出ていって」
/0/16912/coverbig.jpg?v=6094500432b1f7394a537c696ae01d2f)
離婚後、腹黒エリートの愛が止まらない
月城 セナ10年尽くした恋の終着点は、冷たい離婚届と嘲笑だった。 「跪いて頼めば、戻ってやってもいい」——冷泉木遠のその言葉に、赤楚悠はきっぱりと背を向ける。 三ヶ月後、世間が震えた。 彼女は世界的ブランド“LX”の正体不明のデザイナー、億を動かす実業家、そして…伝説の男・周藤社長に溺愛される女。 跪いて懇願する冷家に、彼女はただ一言。 「今の私は、あなたたちには高嶺の花すぎるの」 ——逆転と誇りに満ちた、爽快リベンジ・シンデレラストーリー!
/0/17004/coverbig.jpg?v=9d34d2b07e68e891ef48c799177edf59)
フラれた翌日に結婚したら、億万長者の妻になってました
緋色 カケル失恋の翌日、勢いで見知らぬ男と結婚した七瀬結衣。 どうせすぐ破産すると言う彼を支えるつもりだったが——なぜか彼は異常に頼れる。 ピンチのたびに現れては完璧に解決。どう見ても“運だけ”じゃない! 実はその正体、世界一の大富豪・朝倉誠司。 「これが君の“運の良さ”だよ」 ——波乱のスタートだった“契約結婚”は、いつしか本物の愛へと変わっていく。
/0/18034/coverbig.jpg?v=63ff8b3a25ffd30a75f58fd39800ca48)
愛を諦めたあの日、彼はまだ私を手放していなかった
ぷに林めい結婚二年目、赤子を宿した白川明澄に届いたのは――離婚届。そして交通事故、流れる血の中で彼に助けを乞うも、腕に抱かれていたのは初恋の人だった。命と心を喪い、彼女は静かに目を閉じた。数年後、「白川明澄」という名は藤原誠司にとって禁句となった。彼女が他の男と結婚式を挙げるその日、彼は叫ぶ。「俺の子を連れて、誰と結ばれる気だ?」——愛は終わったはずだった。だが、終わらせたのは誰だったのか。
/0/18578/coverbig.jpg?v=d825d81c3f26bc4d49160333a14171fd)
最強奥様、裏も表も顔を持つ
雛菊ひな【ダブル強者+本物の令嬢?名門?極道の女王】 国際最強の武器商人・黒崎零時が心を奪われたのは、婚約者に捨てられ「無能」と嘲られる、名門のお荷物令嬢・森田柊音 黒崎零時は正気じゃない――誰が見たってそう思う。ただの見かけ倒しに心を奪われるなんて。 だけどある日突然、森田柊音のまわりには、近づくことすらためらうような大物たちが集まりはじめた。 みんなが口々に罵った。「この妖精はまだ黒崎家に嫁いでもいないのに、もう黒崎零時の恩恵にあずかっている。」 森田柊音を潰せと、無数の人が血眼になって“過去”を掘り返し始めた。 まさか――掘れば掘るほど、彼女の素顔がとんでもなかった。 世界を驚かせた天才科学者、 伝説の医師、 そして冷酷無慈悲な手腕で恐れられる裏社会の次期ボス……全部、彼女だったなんて。 ネットが騒然、財閥が震えた。 その頃―― その夜、最強の軍火商・黒崎零時が弱々しく投稿した。「嫁が俺を毎日、敵みたいに警戒してる。どうすればいい…頼む、誰か教えてくれ」
トップ
 GOOGLE PLAY
GOOGLE PLAY
/0/19602/coverbig.jpg?v=84d75c28fb25c8a6d4dfd361737da625)